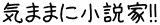短編小説 光らない星
短編小説 光らない星でも、何億年もの間、わたしはずっとこうやって光ってきた。
なんの意味があるのか分からないまま、ずっと光ってきた。
それがふと、嫌に思えた。ついさっきのことだ。
何故だか分からなかったが、こうしてただ浮いて、光る時間に嫌気が差した。わたしはもうここで光っていてはいけない時期なのだ、と自分をさとした。
あるべきところへ行きたいと願う。
しかしそれは、永遠に叶うことは無いだろう。
なぜなら、わたしは自分を束縛していないから。
もしもわたしが何億年も前に生まれたときに、自分を束縛できる力を持っていたら、苦労はしなかった。何人の人間が死に、何匹の生物が生まれても、わたしはそれをはるか上の広い広い空間からながめるしか出来ない。
自分を束縛すれば、それから解き放たれたいと思えばそうすればいい。
何かを思うのも、願うのも自由だろう。
ただ、わたしはそれが出来ない。自分を束縛することは二度と出来ないだろうし、しようと思っても出来る能力が無いのは十分承知だ。
だから何も考えずに、ただ光っているだけがよかった。
それからまた年月は流れた。何十年、何万年、そんな時間が経っただろう。
はるか下で自分を束縛している生物たちは、あちこちを動き回り、今この瞬間に命を失ったりしているのだろう。
そんな時、頭上から声が聞こえた。
………もう、光らなくてもいい。
……二度と光りたくないなら、それでもかまわない。
思いを口にすることが出来ないわたしは、心の奥底からそれを肯定した。
途端に、わたしの全身の力が抜けていった。それが体なのかどうかも定かではなかったが、それを考える余地はなかった。
わたしは意志も心も失った。
同時に、きらめくことも出来なくなった。
これからは永遠に、いつまでもこの広く青い空間のどこかを漂っていればいいと思うと、光を失ったことさえこの上ない幸せに感じられた。