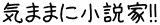短編小説 弟と
短編小説 弟と3年後、再び僕に弟が出来た。お母さんはその時、25歳だった。
だが、再び弟は死んだ。僕はその時、7歳だった。
幼いながらに命の儚さをしった僕は、一晩中泣き続けていた。お父さんは、その時もう既に僕のお父さんではなくなっていた。
あれから5年が経った。
許して、と言ったお母さんの顔が忘れられなかった。けれど、弟達の顔は思い出せなかった。記憶には焼きつく暇がないほど、僕らの過ごした時間が短かったということだろうか。
お母さんは今、32歳だ。だが3年前、お母さんが体調不良を訴えて入院してからすぐ、お母さんの顔を見ることは二度と出来ないだろう、と病院の外科医に告げられた。お母さんの病態を詳しく知ることは出来なかった。面会は病院側で中止されていた。
僕は今、いとこの家で暮らしながら学校に通っている。ずっとこの家で、この地で生きる。誰に言われなくてもそのくらいは悟っていたつもりだった。
ある朝、電話の呼び鈴が部屋に寝ていた僕を静かに起こした。
まだ誰もおきていないようだった。
「はい、山野です」反射的に受話器をとっていた。
相手は、少しの間黙ってからよびかけてきた。
「お兄ちゃん」
僕はその響きになつかしさを感じた。理由もなく、なつかしさを感じた。
「お兄ちゃん」
もう一度きこえたその言葉には、先ほどの声より幼い印象を受けた。
「来て」
「来て」
2つの声が、僕の鼓膜に優しく語りかけた。
「行くよ」
僕が答えると、その電話は切れた。
いつもの時間に家を出ると、途中で近くを通る公園に二人の男の子を見つけた。幼稚園児くらいの男の子が二人、木陰のベンチに並んで座っていた。色ちがいのシャツに同じ短パン、二人は一緒に同じ方を見てにこやかに笑っていた。
僕はゆっくりとその二人に近づいていった。
あと5mというところまで近づくと、二人は同時にこちらを向いて満面の笑みを浮かべた。何かとても大切なものを見つけたような顔をして。
二人は同時にベンチから飛び降りて、駆けてきた。
僕は立ちすくんでしまって、その場にとどまっていた。二人はすぐに、無邪気に抱きついてきた。
「お兄ちゃん」
幻影なのか。それともここは……。
「大丈夫」と、大きい男の子は言った。
「僕らが勝手に遊びに来たの」
「お父さんが僕らのところに来たんだ」
「お母さんのこともきいたよ」
「でも、もうすぐお母さんと会えるよ」
僕は目頭を熱くして、とっさに瞬きをした。
だが、二人の姿はどこにもみあたらなかった。
二人の予言どおりに、お母さんとも面会できるようになった。
「いろいろ大変だったんだね」
僕が学校帰りに病室に立ち寄ると、お母さんは首を振った。
「もう、大丈夫」
これも幻影なのか。僕は瞬きをせずに入られなかった。
ベッドの向こう側。そこに二人の少年が、笑いながら立っていたのだから。