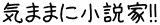短編小説 最期の晩餐
短編小説 最期の晩餐「ずっと前から相談してたの。今の店は閉めるわ」
「今日は閉店日だから、最後のお客として来てほしいんだ」
「今日の午後六時、貸切にして待ってるからね」
前菜として運ばれてきたスモークサーモンと京野菜のサラダにフォークをつきさすと、父は渋い顔で口を開けた。
「あいつも、なかなかいい店を開いたもんだよな」
母はかなり速いペースで前菜を口に運びながら、うなずいて同調した。
「わたしのセンスが良いんですよ。あの子たちがあなたから授かったのは知識だけね」
前菜の皿が妹によって片付けられると、今度はコーンスープが運ばれてきた。二人は同時にスプーンを握った。
「これだけ味がいいのに、店を閉めるだなんて。後先を考えないところもあなたに似てしまったわ」
スープをすくうカチカチという音だけが店内に響き、父の顔をさらに渋くさせた。
「それがあいつらの決めたことなら、否定するつもりはない」
「わたしだって……」
母は反論をしようとしたが、妹によって運ばれてきた白身魚のムニエルをみるなり、黙り込んだ。父は負けじと先に口を開いた。
「この味なら、外国で十分に通用する。文句は言わん」
「そりゃ、才能があるのは喜ばしいことよ。でも生活が大変よね。あの子たちには毎月、生活費を送ってやるつもりだから」
その生活費の大半を自分が働いてかせぐことは、父も十分承知だった。まもなく白身魚は彼らの胃袋の中におさまった。
次に運ばれてきたのは鶏肉のグリル野菜添えだった。
「相変わらず、食べるのが速いわね。やっぱり、シェフだからかな」
鶏肉をテーブルに置きながら妹は笑った。
父と母は顔をみあわせ、ちょっと口元をほころばせてから鶏肉をほおばった。これが自分の息子が作った料理であることに、誇りを感じているようにも見える。
「閉店だなんて惜しいな……」
父は改めてため息をついた。母も今回ばかりは何も言わなかった。
「大丈夫。終わったらすぐに帰ってきて、また店を始めるわよ」
彼らのテーブルには、皿に置かれた柔らかなパンがひと欠片ずつ残っていた。
「食後のデザートは、苺のアイスクリームか甘栗のモンブランのどちらをお持ちしましょうか」
妹は丁寧にたずねてきた。
「苺のアイスクリームをいただくわ」母はすばやく言った。
「モンブランを」と父も続いた。
「かしこまりました」
やがて、パンもなくなった二人のテーブルに、デザートが運ばれてきた。二人は去っていく妹の後ろ姿を見送りながら、感慨深そうにスプーンを手に取った。
「これが、最後の料理だな」
父は栗の甘さにほおをゆるませた。向かいの母も満足そうだ。これからの生活に、いくらかの安心を持てたのは確かであると父は思った。
やがて店の奥から兄が出てきた。その横には妹も立っていた。
二人は食事の手をとめて二人をみつめた。兄は一礼してから、口を開いた。
「僕らは店をやめて、料理のことは忘れることにした。この先、二人で別々に過ごしていこうって決めたから、しばらく旅でもしてまた新しい人生の計画を練るんだ」
都合のいいように勘違いしていたと気付かされ、呆気にとられる二人を戒めるように、兄は重々しく言った。
「最期の晩餐は、お楽しみいただけたでしょうか」