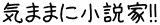短編小説 ツバサとジャングルジム
短編小説 ツバサとジャングルジム五年生の二学期、わたしはお父さんの転勤と共に隣県へ引っ越すことになった。でも、新しい出会いなんてなかった。わたしを待っていた学校では、気のあう友達は出来ない。二ヶ月も経った今でも、わたしは皆がはしゃぎまわる教室のすみっこで黙って本を読むしかない。
読書という行為は孤独のオーラを隠してくれている気がする。何か動作をしていないと、誰とも話さずにボーッとしているのを見られるのは視線が痛いから、せめても動作をしているだけだ。決して、孤独は楽しくない。
本を読むのだって、孤独を隠したいからじゃない。ただ、一人だと読書が楽しい。図書室でみんなが集まる大きな机で読むよりも、教室のすみっこにあるわたしだけが座れる席で読む方が、邪魔もなく読めるし、途中でいらいらしたりしないから、好きだ。
無論、いいわけなのは分かっている。でも、自分の中では認めている。
そんなこんなで、放課後も本を読んでいるしか、わたしには暇つぶしの方法が思いつかない。こんなんじゃ中学でも高校でも一緒だろう。友達も出来ず、一人ポツンと強がって孤独のオーラを隠すフリをする。でも、それでいい。大学になんか行く気はない。高校を卒業した日、誰よりも早く帰って、そのままどこかへ引っ越そう、なんて考えている。
結局、自分が孤独なんだと認めている。正直、群がっている中にいるよりは一人でいると凛としていてマシじゃないかとまで思う。けれど、現実はそんな考え認めてくれる人なんて誰もいなくて、だから避けられたりする。
結局、誰でも味方がほしい。
近所の児童公園は、まさに殺風景だ。敷地は広いのに、中には低い鉄棒と、錆びれたジャングルジムしかない。
この公園が孤独だから、わたしが放課後の長い時間をうめるのには格好の場所だった。誰も来ないから、本を読んでいると本当に一人になれる。
自分ではこの生活スタイルが時代遅れだとか寂しい独り者だとあざ笑えない。好き好んでやっているから、他人はほっといてくれたらいいじゃないかと主張する。独りぼっちの子を見て「あー、独りぼっちでカワイソー」と哀れむの、そんなに楽しいものだと思っちゃいない。
かといって、誰もがその子に話しかける勇気がもてない現実もわたしは知っている。公園には授業が早く終わって暇な低学年の子がたくさん遊びに来るが、誰もかまってくれたことはない。兄や姉をみて、その真似をしていないとはいえない。
「お姉ちゃん、何年生?」
と突然声をかけられたときは本当にビックリした。
その子はまだ真新しい黄帽をかぶり、大きな丸い目をくりくりさせながらわたしをのぞきこんでいた。
でも、人に話しかけられるのは悪いものじゃない。とっさに、
「五年生」と口から言葉が出てしまった。会話するのは久しぶりだった。
女の子はわたしの座っていたベンチに真っ赤に光るピカピカのランドセルをおろしながら、
「わたし、長谷川未来。よろしくね」
と可愛い自己紹介をして、はにかんでみせた。
「わたしは……」
自己紹介をするのを思わずためらっていると、未来ちゃんはそれを待たずにジャングルジムのほうへ駆けていった。
「ほらほら、見て!」
わたしは名乗らないままだったが、未来ちゃんはさほど気にしていない様子だった。自分でこちらに話しかけては、「見て見て!」と叫んでジャングルジムで遊んだ。
ジャングルジムの中で棒にぶら下がったり、ジャングルジムの少し高いところから地面に飛び降りたりと楽しそうに遊ぶ。
一週間ほどして、未来ちゃんのランドセルの位置を観察していて気付いたことがあった。他の子のランドセルから、少し離れた場所に置いてあったのだ。そして、誰ともしゃべっていない。なのに彼女は無邪気に遊んでいた。毎日、目をくりくりと回して、輝かせて。
そんな姿を見ていたら、未来ちゃんに直接「独りぼっちなの?」とはとうてい訊けなかった。
独りぼっちの環境にも負けない未来ちゃんは、やはり好奇心旺盛らしい。
「ねえ、あそこにのぼるから見ててね」
週末、学校が休みに突入する金曜日。未来ちゃんは突如ジャングルジムの一番高いところを指差して、元気よくジャングルジムにのぼっていこうとした。でも、わたしはとっさに「危ないよ」と言って、ちょっと強引に未来ちゃんの肩をおさえた。
「落ちてケガなんかしたら、お母さんが心配するよ」
未来ちゃんは腑に落ちない顔をしていたが、しばらくするとジャングルジムの低いところでいつも通り遊び始めた。
次の週の月曜日、公園に未来ちゃんの姿は見当たらなかった。誰もが帰ろうとしている時間でも、未来ちゃんの姿はない。わたしはちょっと不安になって、一人で帰ろうとしている未来ちゃんと同じくらいの年齢の子に話しかけた。
「ねえ。長谷川未来ちゃん、知ってる?今日、学校来てた?」
女の子はちょっとビクッとしてから、ちょっとうつむいて、そして顔を上げた。
「未来ちゃん、土曜日に死んじゃったよ」
思いがけない児童の言葉に、わたしは息を詰まらせた。
「えっ、何。……何でよ、事故?先生にきいたの?……ねえ、それホント?」
女の子はためらわずに、素直に答えてくれた。
「本当だよ。先生が、言ってたもん。他のクラスの先生も言ってたの。未来ちゃんね、お父さんがいないんだよ。小さい時に亡くなったんだって。友達にきいたの」
女の子は小さな手でジャングルジムを指差した。自然と視線がジャングルジムの一番高い位置にいった。未来ちゃんが行きたがっていたところだ。
「お父さんは空の高い高いところから見てるから、少しでも高いところに行きたいんだって」
わたしは呆然とジャングルジムを見つけた。
幼い少女はそれに気付かず、続けた。
「高いところに行けば、お父さんに近づけるからって。だから未来ちゃん、ジャングルジムのてっぺんにのぼって、落ちちゃったんだって」