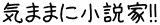短編小説 わたしの師匠
短編小説 わたしの師匠でも、世間が言う「女の子」とは違う気がするんです。なんだかこう、輝き方がちがうっていうか。きらびやかな生活とは無縁の人間なんです。
それがわたしの一番の悩みでした。
わたしのクラスには、学級委員長が男女ひとりずついます。女子の学級委員長は、ミサコちゃんという子です。
男子のほうの名前は知りませんでした。わたしは、名前とかすぐにおぼえないし、クラスのほとんどの男子の名前を知りませんでした。
教えてくれたのはミサコちゃんでした。
ミサコちゃんにはとても感謝しているし、感謝しきれません。
「あーっ、島元さーん!」
保健室にいたわたしは、苗字を呼ばれて振り向きました。ドアのところに、ミサコちゃんが立っていました。
わたしがおろおろしていると、上靴をぬいだ彼女はずかずかと保健室にあがりこみ、わたしの座っている椅子の前まで来て、大きな口をあけてこう言いました。
「さっき廊下で生徒手帳ひろったで。はい」
関西出身の彼女は、関東の学校に来ても関西弁をあやつり、他の生徒からも人気者でした。父親が以前漫才師だったとかで、お笑いのセンスも持っていました。
わたしは彼女に近寄りがたかった。わたしはあまりお笑いが好きではなかったし、笑うこともそんなにいいことだと知らなかった。
でも彼女はおかまいなしでした。
「なぁ先生、ここの保健室どうなってるんよ」
「えっ、どういうこと?」
急に話をふられた保健室の先生はあわてていました。
「このベッド、スプリング壊れかけてるやン。寝心地ぜんぜん良くないし、治るもんも治りませんよ」
先生はくすくすと笑いながら、校長先生に相談してみるわと冗談を返していました。
「何で来たの?」
わたしが初めてミサコちゃんにしゃべりかけたのは、この時です。
ミサコちゃんは「んー?」と言って笑いながら、
「暇やったから」と答えました。
暇つぶしに保健室を使って、そこで笑っていられる人間がいたのか!
わたしは大発見をしたような気持ちで、ドキドキがとまらなかった。
次の瞬間。
「師匠になってください」
真面目な顔、真剣な気持ちでそう伝えました。
初めて話した二言目にそんなことを言われて、ミサコちゃんは当惑したような表情でした。あたりまえ。すみません、冗談です、とそう言おうとしたら、
「ええよ」
とミサコちゃんの声がきこえました。
「うちが師匠で、島元ちゃんが弟子ね。うん、分かった」
……島元ちゃん?
わたしは頭の中がグルグルしていて、もう何が何だか。
「うちが笑いのセンス、島元ちゃん……言いにくいなぁ、しまもっちゃんに教えてあげるわ」
教えて欲しいのは笑いのセンスじゃなかった。
だけど、そんなことはどうでもよかった。
二言目には師匠になってくれた、弟子にさせてくれたミサコちゃんが、何より嬉しかった。
卒業式の日。
ミサコちゃんと出会ってから、もう丸二年。
ミサコちゃんは、関西の私立高校に進学するので、大阪に戻る。
ミサコちゃんに弟子入りしてから、生活は劇的にかわったわけじゃない。ただ、じっくりじっくり「自分」をつくれてきたような気がする。
「しまもっちゃんは、うちの一番弟子やから、いつでも呼びや!」
そういって、師匠は生まれ故郷に帰っていった。