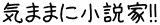短編小説 アンブレラ
短編小説 アンブレラわたしたち出会っていなかったよね。
バレンタイン当日、わたしの心を映したかのような曇り空の中で、わたしは始発電車を待っていた。
家が田舎なもんで、高校へいくのには始発電車に乗らなければ間に合わない。
ようやく旧暦でも春がおとずれ、日も長くなってきた。
ホームで電車を待つ私が持っている、手提げのサブバックの中には、昨日つくった生チョコがたくさん。
ちょっと残念なことに、全部友チョコ。
突然もらったときのために、数人分は多めにいれてある。
高校生になってから、なんとなく恋愛には興味がわかなくなってしまった。理由は分からないけど、なんだか頭の中がリセットされたみたいで。
誰かがわたしに恋をしてくれたら、それはそれで現実もわたしも変わるんだろうけど、そんなことはないから結局そのまま。
今はいいんじゃないかな。
そのうちもうちょっと大人になったら、きっとカバンの中にたったひとつとびきりのチョコレートを入れて、電車を待つ日が来るだろうから。
学校へ着いた途端、わたしの席はチョコレートやクッキーを交換し合う友達でうめつくされた。どの子のラッピングもかわいくて、わたしのシンプルな袋と金のモールなんて素っ気なさすぎじゃないかと思うほどだった。
「ごめん」と思わず口に出した。
友達はみんな、なんで?と言った表情でこちらを見つめ返してくる。
わたしは思っていることを素直に言った。
「玲はそういう飾りっけないとこがいいの!」
それを聞いて、友達ははにかみながらそう言ってくれた。
「ありがと」
なんだか曇り空だけど、心はあったかい。
それは、同じようにあったかい友達がたくさんたくさんいてくれるからなんだ。
昼休み、彼氏にチョコを渡しにいくという友達が教室から出て行くと、わたしのグループの子たちはその話題で持ちきりだった。
「彼氏って、3組の小澤くんだよね」
「らしいよ。サッカー部の人だよね?」
「うん」
「わたし一緒に帰ってるとこみた。二人ん家、わりと近所だし」
このグループで恋バナになると必ず盛り上げてくれるのが、今彼氏に会っているであろう早紀だ。私立中から出てきた早紀は、入学してからすぐにサッカー部のマネージャーになり、夏から小澤くんという部員と付き合っている。
中学校は隣で、早紀は私立中だから全然交流はなかったのだそうだけど。
「あっ、雨降ってる」
何気なく外を見ると、ぽつぽつと雨がふってきた。
ほどなく早紀が帰ってきた。
「おかえり〜」
「気付いた?雨降ってるよ」
「うん。あいあい傘の約束してもらっちゃった」と早紀。
歓声とか悲鳴とかが、いろいろ混じってわたしたちを包んでいく。
帰る頃にはザーザー降りになっていた。
早紀は家まであいあい傘、他の友達は折りたたみや置き傘があって助かったんだけど、一人遠くまで帰らなければいけないわたしは傘がなく、急いで駅へと走った。
カバンやコートについた水滴を気にするひまもなく電車にすべりこむ。
早い電車に乗らなければ、そのぶん帰るのが遅くなってしまう。
電車に揺られながら、母に迎えに来てもらうようにメールをする。
家から最寄の駅に着くと、母に頼んだ時間より10分ほど早かった。
出入り口の近くで雨宿りをしながら母の車を待つ。
そのとき、出入り口の反対側に見慣れた人影をみつけた。
中学校のとき同じクラスの徳田くんだった。
片想いで終わったけど、ちょっと好きだった、徳田くんだった。
徳田くんを見ていると、ちょっと目があった。
相手もこちらに気付いたようで、でも用はないようで。
二人ともしばらく黙っていた。
やがて、駅前の赤信号で止まっている母の車が見えた。
右に、一歩踏み出す。
「……これ」
軽くなった手提げカバンから、予備だったチョコを一個差し出す。
なんだか自然な足取りのままで、むしろ相手を緊張させてしまっていた。
「えっ、おれ?」
「……うん、そうだね」
徳田くんはそれでも受けとろうかどうか迷っているようだった。それでも、そっと受け取ってくれた。
そこで、彼がここにいた理由にようやく気付いた。
「徳田くん、傘もってないじゃん」
徳田くんは、忘れたからバス待ってんだよ、とサラリと風のように言った。
「そっか……じゃあ、また」
「ああ」
母の車が近づいてくるのをみて、わたしは慌てて彼と別れた。
『また』会うことなんてあるんだろうか。
偶然とか運命じゃないかぎり、こんな雨の日は二度とこない。
それでも朝とは違って、傘のないわたしの足取りは軽かった。