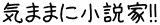短編小説 ずっと、ずっと、演じてきたもの 〜前編〜
短編小説 ずっと、ずっと、演じてきたもの 〜前編〜わたしはめいいっぱいの声を張り上げて、悲痛な声をだす。
明るい光がわたしの頭上から降ってきて、あまりにまぶしい。周りは暗闇。ほとんど、人の輪郭くらいしかわからない。
それでも、自分がその中で注目されていることを知って、だから大きな声でわたしはつづる。
「わたしは、嘘つきはきらいよ・・・!」
目の前にいる青年が、そのせりふに少しだけ顔をゆがめる。
そして、おおげさに、額に手をあててみせる。
「きみ・・・、きみという人は、どうしていつも、そう、正直になれないんだ?」
青年は、スポットライトの照らす壇上から、客席のほうを見下ろす。
わたしはまだ青年のほうを向いたままで止まっている。いま、わたしはそこから動いてはいけない。
そして、悠々とした声で、このシーン、最後のせりふを言う。
「ぼくは・・・正直なきみが好きだよ」
青年は、やり終えた、という顔で、満足そうに小さく微笑む。
わたしは満面の笑みで、青年にかけよる。
今日の舞台も、大成功だった。
わたしは楽屋で、笑顔で仲間たちと語り合いながら、ほくそ笑む。
もう十年以上、劇団員をしている。
今回の劇でわたしの相手を演じてくれた青年は、わたしのひとつ年下の後輩の団員だった。大学に通いながらこの劇団に通い、卒業してすぐに、こうして主演に起用された。
わたしは、主役を張るのはこれで数回目だった。
「はっちー、おつかれさま」
後輩の八野浩介に声をかける。さっきの”青年”である。
劇団の仲間はみんな、彼を”はっちー”と呼ぶ。”ハチ”だと犬みたいだから、という理由からだ。
「お疲れ様でした、未央先輩」
わたしはやりきった顔で、笑顔をふりまく。
「先輩、いつもめちゃくちゃ元気なのに、舞台になるとあんな悲しい声が出せるんですからねー。さすがっす」
八野は、あどけない顔で笑ってみせる。彼は劇団なんかにいなかったら、スポーツマンタイプで、きっとテニス部なんかに入って、女子の先輩にちやほやされるのだろう。
そんなことを考えながら、わたしは、ううん、と首をふった。
――彼は、本当は知らない。
「何、はっちー。ほめても何もでないよ! それにわたし、けっこうネガティブだし」
「またまた。先輩がネガティブなとこなんて、見たことないっすよ」
はは。
ははは。
笑う。
うん、今までもずっとこうしてきた。
ポジティブで、いつも笑ってて、努力家で、ユーモラスな、後輩から慕われる、明るい先輩団員。
劇団のみんなはわたしをそう表現してくれる。
わたしはネガティブで、といえばいうほど、「うっそだー!」と言って、信じてもらえない。
いや、信じてもらわないとわかっていて、わたしは「ネガティブ」と言い張ってきた。
それでわたしが保たれるのなら・・・、と。
わたしは数年前、学芸大学を目指していたが、ことごとく受験に失敗。
そしてその失敗に目をそむけ、以来、劇団員ひとすじで頑張ってきた。
小学生のときにこの劇団に出会い、以来小さな役をつとめながら勉強してきた。
高校で演劇部に入り、将来も演劇の道を志していたわたしにとって、この劇団は大切な居場所のひとつだった。
今回の舞台は、オーディションに同席していた脚本家の方に、ぜひ主役をしてほしいと頼まれ、快くそれを引き受けて実現したものだった。
昔からいるメンバーも、劇団にいるわたしと、舞台にいるわたししか見ていない。
私生活のわたしを、知らない。
わたしは、ずっと前から、自分が自分以外の何かを演じていることに麻痺している。
いくら舞台の上で、生身のお客さんを相手にしていても、やはりその感触はぬぐえない。
でも、劇をしていると、そのことは忘れてしまう。
失敗に目をそむけたように、わたしはわたしの内面について、目を背け続けているような、そんな気がしている。
…to be continued