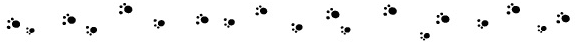▼1
「深度98m、99m、100mに達しまいした。」緑色の光が鈍く光るコントロールパネル。
目まぐるしく変わる数字とアルファベッドとあらゆるグラフ。
その前で軽くキーを叩きながら黒髪の青年は、後で控えている様々な国籍のスタッフに指示を出す。
「地震計に反応は?」
「ありません。」
「地下水脈が南西方向に伸びていますが、問題無いようです。」
「よし。そのまま今のスピードを持続してさらに下降させる。甲太郎、いいな?」
青年はインカムを引っ張り、今現在ロゼッタ協会が発見した地下神殿入口近くに達している皆守甲太郎に指示を出す。
前面に大きく広がるモニターに皆守が見ているであろう景色が広がっている。
皆守の足のすぐ下には神殿の入口らしき石版で封じられた扉。
そして竪穴の狭い壁には目まぐるしく動く、明らかに超古代文明によって作られた電子パネルが収まっている。
「ああ、今のところ何の反応も無い。至って順調だ。」
「頼むぞ甲太郎、お前の動体視力だけが頼りだ。」
どうやらこの目まぐるしく動く電子パネルが神殿の鍵となっているらしく、人よりもはるかに優れた動体視力を持つ皆守が今回のミッションの尖兵として送られたようだ。
「任せな、九ちゃん。」
皆守はそう答えて目の前の電子パネルに指を触れる。
ハッピーライフ
「では迎えに行こう。」
そう言って葉佩達ロゼッタのスタッフは車から降りる。
きりきりと音を立てて、葉佩達の前でゆっくりとアンカーが引き上げられる。
暫くすると調査の為に地面の掘られた狭苦しい竪穴から、砂にまみれた皆守が姿を現した。
その無事な姿を見て葉佩はほっと安堵の息をもらす。
引き上げられた皆守は素早く安全ベルトを外し、そのまま真っ直ぐに葉佩の方へと歩いてくる。
他の者には目もくれずに。
「お疲れ…って甲太郎?!」
葉佩阿労いの言葉をかけようとした瞬間、皆守は先ほど手に入れた古代の遺物を無造作にスタッフに放り投げたのだ。
「うわーーーッ!」
投げられた遺物をスタッフ慌てて寸前のところで受け取り、周りのスタッフから拍手が起こる。
「甲太郎!何てことッ!!!」
葉佩はその行動に抗議の声をあげようとしたが、皆守は構わず葉佩の元へずんずんと進み文句を言う葉佩に構わず葉佩をがばりと抱きすくめた。
「甲太郎ーーーッ!お前何ッ!!」
「約束した。この仕事を成功させれば九ちゃん俺のいう事何でも聞くって言った。」
そのまま反論を言おうとする葉佩の口を素早く自分の口で塞ぐ。
「んんーーッ!!」
充分唇を堪能した皆守はそのまま葉佩を抱える。
「ちょッ!ちょっと待て甲太郎!!」
腰がくだけてたっていられない葉佩を皆守はひょいと抱えてキャンプトレーラーに移動しはじめた。
そして遠く、葉佩の罵声がキャンプトレーラーに消えるまでの一部始終を、皆守から遺物を受け取ったスタッフが呆然と見詰めていた。
「おーい、新入り、早くそれケースに入れろ。」
遺物を皆守から受け取ったスタッフがいまだ呆然としていると、後からベテランのスタッフが声をかけてきた。
その声で呪縛が解けたように、ビクリと身体を揺らして奇声をあげた。
「え、ええ?ええええーーッ!!あ、あのあののあのッ!」
「落ち着けって。」
取り乱す新人スタッフをベテランとおぼしき白髪のスタッフが肩を叩く。
「あ、あれ一体難なんですかーーーッ」
見れば彼以外のスタッフは何事も無かったように各々の仕事をこなし撤収の作業に入っていた。
「ああ、お前アレ見るの初めてか?まあ彼らのスタッフに付くんなら覚えておけ。」
そこでベテランスタッフはびしりと指先を立てて、言い含めるように新人に警告したのだ。
「アレは日常茶飯事だ。慣れろ。」
「い、意味が分かりませんッ!何で葉佩さんと皆守さんが、ええと…ごにょごにょ……になってるんですかーーーッ!!」
「ランキング一位のトレジャーハンター葉佩九龍とその専属バディの皆守甲太郎は、まあその、見てのとおりなんだよ。」
そこに何故か嬉しそうに話しに加わる女性スタッフ。
「そうそう、しかもあの甲太郎は腕は確かでもうハンター資格とってるのに葉佩のバディしかやらないの。愛しちゃってるのねv」
「まあ甲太郎は腕が立つのは確かなんだが、仕事をあまりしたがらないんでな、その手綱をとれるのは葉佩しかいないんだ。」
「ま、それで仕事が終わるとまあ毎度のアレが見れると……」
「……納得いきません。」
「え?」
それまで黙って話を聞いていた新人スタッフは地の底から響くような声でぼそりと呟いた。
「俺は九龍さんに憧れてやっと専属スタッフになれたのに、やっとここまで来たのに……あ、あんなの納得いかねーーーッ!」
ずんずんと歩く新人に、ベテランスタッフは後ろから止めの声をかける。
「ああ、30分はトレーラーに近付くなよ。」
「どういう意味ですかーーーッ!」
「……そういう意味だよ。」
顔を真っ赤にして怒れる新人を、老練なスタッフは哀れみの目で見つめていた。
「……また、スタッフに呆れられる。」
ぐったりと白いシーツに顔を埋める葉佩が、情けなさそうに呟く様を皆守は面白そうに見つめていた。
「いいじゃん、もう恒例になってんだからよ。」
自分の髪を玩ぶ皆守の手を払いのけて葉佩は怒りを顕にした。
「どうしていつもそう即物的なんだよッ!ちょ、ちょっとの間待ってくれたっていいじゃないか……何も、い、嫌だとは言わないんだから。」
「だったらいつでもいいだろう。」
「良く無いッ!」
「俺はいつも九龍に触れていたんだ。」
「……」
そう言われれば葉佩は黙るしかなかった。
黙ると分かっていて皆守は必ず最後にこう言うのだ。
だからといってその言葉に嘘偽りは無い。
その真摯な気持ちが分かるからこそ、葉佩は黙るしかないのだ。
黙ってしまった葉佩の髪を、頬を皆守の大きな手が優しく撫でていく。
「いいじゃないか。どんな所でも、どんな状況であろうと、俺はお前に触れていられれば幸せなんだ。」
触れていないと、逆に俺の人生はなんと不幸なことか……
皆守は促すように葉佩の頬に手を当てて自分の方へと向けさせる。
そして唇が触れようかという瞬間、けたたましくとレらーのドアを叩く音が響いた。
「九龍さん!セーンーパーイーッ!!トランクの暗証ロック、九龍センパイの指紋パターンが無いと開けられませーん!!早くそんなモノは捨てて出てきてくださーい!!」
「あ、凍矢。」
「……あんのやろう。こんな所まで追ってきやがって……。」
まだまだ、皆守の完全無欠のハッピーライフは遠いようだ。