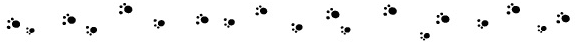▼1
「おや、もうこんなに香りがするよ。」そう一太郎は呟きながら、縁側に鳴家を膝に抱えてほっこりと暖かくなりゆく空気の香りを楽しんだ。
おしつつむ (佐助×若だんな)
「金木犀はほんとに香りがいいね。」
金木犀は香りの強い木である。
庭の木を見る限りではまだまだ緑の葉が覆い茂り、あの金の小粒のような山吹色の花はちろちろと葉っぱの陰に隠れるようにしか咲いていない。
にも関わらず、小さいながらもその甘い芳香を若だんなの鼻筋に運んでいる。
「随分ときつく香りますね。」
そう呟きながら、手代の佐助はこがし湯をそっと差し出した。
ついでに手妻のように取り出したかいまきを、「風邪をひいたら大変です。」と言いながら有無を言わさず若だんなに着させる。
この過保護振りにはいつも一言どころか大いにに文句を言いたいところだが、いつもの事なので言っても無駄、という事を若だんなは学習している。
何より今は、この優しい香りが佐助にとってきつい香りだと言う事の方に、好奇心がうずいた。
「そうかい?ああ、佐助は鼻がいいから、この香りはきついかね。」
言外に、やっぱ犬だから?と語りかけてくる黒い眼(まなこ)に苦笑しながらも、「それもありますがね……」と前置きして語り始めた。
「この香りが、私はあまり好きじゃあないんです。」
佐助の告白に若だんなは大層驚いた。
「そうなの?こんなに良い香りなのに……。」
己が好きなものを嫌いだと言われて、若だんなは少し悲しくなった。
それが顔に出たのか、膝の上で大人しくしていた鳴家達がきゃわきゃわと騒ぎ出し、どうやら若だんなを慰めようと身体をよじ登り、その小さな手で若だんなの頬を優しくぺちぺちと叩いた。
「若だんな若だんな、我はこの香りが好きです!悪いのはこの香りが好きではない犬神殿です!だからそのような顔をしなくていいのですッ!!」
「そうですそうです!」
「きゅわーーーッ!」
最後の声が悲鳴に近かったのは、鳴家達の横行を、犬神さまが許すはずもなく、その小さな身体は無常にも佐助の手によってぺしっと払われた為だった。
「お前たち、若だんなにへばりついて無体をするでないよ。若だんなが倒れたらどうする。」
「佐助、さすがにそれは無いよ……。」
佐助が怒ったのは彼に対する悪口にではなく、若だんなにへばりついた事に対してだったのだ。だがこれも日常茶飯事のこと。
最後の一匹を払い終えたところで、佐助は遠巻きにしながらも自分を睨み付けてくる鳴家を軽くねめつけて、鼻をふん、と鳴らした。
「それにね、私はこの香りが嫌いじゃあないんだ。この香りの強さが嫌いなんだよ。」
「そうなの?この香りがきつくなかったら、好きになってた?」
佐助は若だんなの質問ににっこりと応え、そのまま若だんなのずり落ちかけているかいまきを掛け直した。
「そうですね……ええ、好きになってたかもしれません。この香りはきつ過ぎて、若だんなの香りさえも、押し包むようにして広がるから、私は好きにはなれないかもしれません。」
「私の香り?それは、反魂香の香りのことかい?」
「それもありますがね。色々と混ざり合って若旦那の身体に染み付いた香りです。反魂香と薬湯、日差しの匂いと、ああ、鳴家の匂いも混ざってますね。それら全部が合わさって、若だんなの香りになってます。」
(その若だんなの香りが、きついこの香の中では薄れてしまう……。だから嫌いなんですよ。)
その言葉は、佐助の中で静かに呟かれ若だんなには聞こえない。
「そうかあ……私はそんな匂いがするのか。」
佐助の心中を知らない若だんなは、自分の香りに興味津々なのか、袖を持ち上げてくんくんと嗅いでいる。
その様子を見ていた鳴家達までもが若だんなの香りを嗅ごうと、くんくんと鼻をひくつかせて若だんなに群がる。
まったく、これではどちらが犬が分からない。
苦笑しながらも、佐助は金木犀の香りに紛れそうになる若だんなの香りを懸命に追う。
その香りを感じて佐助の胸がとくん、と跳ねるのが分かった。
ほっこり、ほっこり、
それは犬神が、求めて求めて、やっと手に入れたちょっとせつない香り。