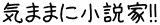Time きこえぬ悲鳴
Time きこえぬ悲鳴診察室の外に出ても麻里はずっとすすり泣いていた。泣いていたらシュリーに申し訳ないと思っても、こみあげてくる涙は止まらない。まわりの視線だって、もうどうでもよくなってきた。――シュリーは家族だから。あんたたちにどう思われてもかまわないよ。
帰ってきた両親に気付くと、一瞬涙をとめた。でも、フリにしか見えないだろう。
「先生、何て?」
大介に訊ねると、大介の口調はしっかりしていた。
「やっぱり季節のこともあって、体が弱っていたらしい。でも麻里はしっかり世話をしていたんだろうって、先生はほめてたよ」
麻里は、返事が出来なかった。――自分を責めているわけじゃない。悲しいだけ。でも、先生はわたしほど悲しくはないはずだ。だって、たくさんの動物の死に遭遇し、その度に飼い主を励ましてきたのだろうから。そんな人間に励まされても、全ての傷は癒えない。
落胆しきった麻里を先に車に乗せ、大介と美月は車の外で話した。
「麻里、大丈夫かしら。やっぱり今回のことでショックを受けているんじゃない?」
「心のケアの方もいるかもしれないな」
大介は車のほうを振り返った。「でも、その内落ち着くよ」
「シュリーの物は、お墓にそなえることにしましょう。先生の言うとおり、庭に埋めてあげるのが一番だと思うわ」
美月はせかすようにそう言った。
悲しいことの連続。まさに心に穴が開いたような気持ちだった。麻里は声を出すのも苦しくなっていた。気のせいだろうが、喉が細くなっていくのが分かる。
涙と一緒に、おさえきれなかった悲しみや後悔が体から流れ出してしまったようで、心には感情がほとんど残っていない。だから、からっぽだった。そこにまた新しい感情が湧き出てきても、全てこらえきれるものではなかった。
「麻里。シュリーのお墓作るの、手伝って」
帰ってきても何もしようとしない麻里に、美月が言う。
思い立ったらすぐに行動を起こすのが美月の性格だった。一度心を落ち着けてから動きたい麻里とはまるで意見がかみあわない。
無言でうなずいて、麻里は庭に出る。迷惑をかけるのは承知で、玄関からわざわざ自分のサンダルを取ってきた。庭に出るために安そうなツッカケがあったが、そんないい加減な気持ちのままでシュリーとお別れをしたくなかった。
「何でわざわざサンダルなんか持ってくるの。そこにツッカケがあるのに」
麻里は言い返す気にもなれなかった。自分で決めたのに、たかがツッカケとサンダルで言い争いする母を嫌に思った。
「今まで、ありがとう」
「ごめんな。俺達が、悪かったのかもしれない」
そんなセリフを、麻里は口に出してはいえなかった。冷たい心の中に、まだ口に出せるほど感情が湧いていない気がした。
それに、自分たちばかりがシュリーに接しようとする両親に、軽く嫉妬の心があった。
シュリーをお墓の穴に埋めて、両親はそっと手を合わせた。
美月はまた少し涙ぐむ。麻里は後ろからお墓を覗き込む。美月はそんな麻里をみて、また声をかけた。
「ほら……お別れなのよ。どうして何も言わないの。すねてるの?悲しいの?何か怒ってるの?挨拶くらいはしなさい、シュリーに失礼でしょ。ほら」
美月が体をどかし、麻里を墓の前に行かせた。
(お母さん、何も言わないで……シュリーが迷惑がるよ)
麻里は心の中で言い返す。
だが、シュリーの顔を思い浮べて呼びかける。
(シュリー。わたしは、シュリーが死んだことすごくショックだったよ。自分に腹も立つよ。苦しかった……?悲しかった……?でも、シュリーが大好きだったのは本当だよ。シュリーなら信じてくれるよね?家族だもん……)
麻里が父親の顔を横目にみると、父親はその視線に気付いて軽くうなずいた。
「麻里」そうよびかけ、大介が麻里にスコップを持たせた。
麻里は静かに庭の土をかぶせていく。同時に、シュリーとの思い出が頭の中によみがえってくる。
「ぁ…」
「明日から、毎朝シュリーに挨拶しようね」と言おうとした麻里の口からは、小さな小さな「ぁ」しか出てこなかった。麻里は以前読んだ、両親をなくした女の子の声が出なくなってしまう小説を思い出した。
シュリーを買ったときには、シュリーが死ぬことなんて考えてなかった。自分の未熟さに、飼い主としての自信がちょっぴりなくなった。
「麻里……」
美月のとげの生えたような声にさらに追い討ちをかけられ、麻里は首を横に振ると、サンダルを脱ぎ捨てて自分の部屋へと駆け込んだ。