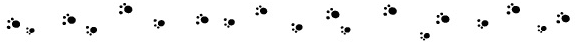▼1
最初は、最初は只の教師と生徒。ただ、それだけの関係だったのに……
その関係は緩やかなカーブを描きながら密やかに、しかし確実に変わっていった。
『高校教師』
初めてその部屋を訪れたのはこの高校に転校してからそれほど日にちが経っていない雨の日だった。
俺はクラスの人数分のノートを両腕に抱えながら静かに廊下を歩きながら、内心は先日のクラスメイトの言葉を繰り返し反芻していたのだ。
彼曰く、
「生物準備室には近寄るな。」
だった。
何故生物準備室が禁忌の領域になっているのかというと、その部屋の主に問題があるらしい。
主の名は犬神杜人。
この真神学園高等学校の生物・物理教諭を務める、外見ちょっとくたびれた先生だ。
クラスメイトの言葉の幾ばくか脚色された部分を除いたとしても、生徒からも、ましてや教師からも嫌煙されているらしい彼の人物像は、俺の中で勝手に肥大化していった。
もう少し詳しく言うならば、今日始めて彼の授業を受けたその感触からも、くたびれた外見とは他所にその内包されている何かしらの鋭さが感じ取れた。
しかも運悪く、今日の生物はノートの回収を命じられ、その担当が日直当番に当たっていた俺に回ってきたのだった。
初対面からも、今日の授業からも決して好印象では無い教師の根城に乗り込む心中は、決して穏やかなモノではなかったのだ。
そうこうしている内に、無常にも俺の足は生物準備室の前に到着していた。
抱えていたノートを抱え直し片手を上げ、一つ深呼吸。
覚悟を決めて俺は扉の戸を叩いたのだった。
「失礼します。」
案の定、扉の中からは生返事が一つ出ただけでだった。
一応主からの許可を受けたので俺は扉を開け中に入った。
最初に俺を襲ったのは、もうもうと立ち込める煙草の煙の匂い。
そして次に棚に並べられた何種類もの薬品瓶の香りと、そして標本から漂うホルマリン液のツンとした刺激。
視覚には山と積まれた本とプリント類が申し訳程度の微妙なバランスを保って部屋の中を席巻している絵と、そして机に向かい煙を吐き出している大きな背中が入ってきた。
「あの……」
俺が小声で声をかけると、机に向かったまま背中で先生は生返事をした。
しかし驚いた事に、見てもいないのに俺が誰だか言い当てたのだ。
「ああ、3-Dの緋勇か?」
その事に驚いた俺は返事を返すタイミングを逃し黙っていると、漸く先生がくるりと椅子を回転させて俺の方に向き直った。
「どうした?ノートを持ってきたんだろ?」
振り向いた先生は心なしか先ほどの授業の時よりも無精髭が伸びたような印象を受けた。
まさか一時間ほどで髭が伸びるわけも無く、何故その印象を受けたかはすぐに知れた。
先生が咥えている、今も遠慮無しにもうもうと煙を吐いている煙草のせいなのだ。
「ご苦労だったな、適当にその辺に置いといてくれ。」
そう言われて周りを見渡してみても、ノートを置ける場所は見当たらない。
仕方なく応接用の机の上に乱雑に積み上げられた雑誌を適当に片付けることにした。
「先生、この机の雑誌、どかしてもいいですか?」
「ああ、かまわん。」
先生の許可を取って俺は机の上の雑誌を片付け始めた。
とはいえ、かなりの量に加えやたらと種類も多いそれらの雑誌を種類ごとに並べて再び積み重ねるのは結構手間だった。
そんな俺の様子を見た先生は半ば呆れたように話し掛けた。
「おい、そんなもの適当に床に置いておいてもいいんだぞ。」
「でも、何か……」
ざっと見ただけでも英文で書かれたちょっと高そうな雑誌や、見ただけで専門雑誌と分かるタイトルの雑誌を見ると、どうも無下に扱うのは心苦しい。
なんとも小市民的な心理と、担任ではないとはいえ、先生の雑誌を無下に扱うのは心苦しいのだ。
そう俺が告げると、やはり呆れたような口調で一言。
「好きにしろ。」
というと再び机に向き直ってしまった。
まあそこまで言われたので心置きなく俺は雑誌を片付けた。
時間にして5分程度だったと思う。
そんなに労は無かったのだが、片付け終わるタイミングを見計らったかのように目の前に温かな湯気を出す珈琲が出された。
「悪かったな。雑誌の片づけまでさせて。」
正直、俺はびっくりして声も出なかった。
これは俺が勝手に始めた事。
それにノートを置くには片付けなければいけなかったし、先生ならば生徒である俺に気を使う必要は無いのだ。
そして最初の印象が悪かった分、この差し出された珈琲にはかなりびっくりした。
「どうした?嫌いだったか?生憎とここにはこういうもんしか無いんでな。」
引かれようとする珈琲を折れは慌てて受け取った。
「あ、ありがとうございます。」
俺は珈琲に口をつけた。
途端に広がる苦味。
その苦味が顔に出たのか先生はクスリと笑った。
馬鹿にされた、かな?
でも苦手なモノは苦手なのだ。
「あのー、砂糖なんてものありますか?」
「無いな。」
やっぱり先生はイメージどおりブラック党のようだ。
俺が珈琲を睨んでいると、不意に先生が思い出したかのように俺に告げた。
「ブドウ糖液ならあるぞ。」
はたして真面目に言っているのか、はたまた俺をからかっているのか。
先生の顔を見ると、ニヤニヤ笑っていた。
「遠慮します。」
この日、それまで抱いていた俺の先生に対するイメージ画大分変わった。
見た目は怖いけど、でも良く見ると結構渋い顔をしている。
生徒の俺にもちゃんと礼儀をもって接してくれる。
それと以外に茶目っ気があること。
そして次に俺が生物準備室に行くと、そこにはちゃんと2〜3本のスティックシュガーが用意されていた。