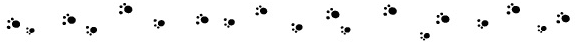▼2
その日、俺は急ぎの事務仕事に追われ珍しく職員室で書き物をしていた。職員室には俺の他には養護の女性職員しかおらず、いつも忙しない部屋が閑散としていた午後のひと時だった。
『高校教師』 砂糖菓子
面倒な事この上ない事務仕事に、犬神のイライラとした雰囲気が伝わったのだろう、その養護の女性職員がそっと犬神の机に香り立つ紅茶を差し出した。
いつもは珈琲の芳ばしい香りが好みなのだが、たまには紅茶の控えめな甘い香りも悪くないと珍しく思いながら、犬神は短く女性職員に礼を言うとカップを持ち上げた。
「あ、犬神先生。お砂糖とか入れますか?」
犬神が紅茶を口に運ぼうとした時、女性職員は何か思い出したようにパタパタと自分の机へと走り、何かを手にして犬神の前に差し出した。
「実は姪が結婚式を挙げましてね。その引き出物に入ってたものなんですけど、今時珍しいでしょ?」
そう言って差し出されたのは、綺麗に花を模られた小さな砂糖菓子だった。
確かに、今時の結婚式の引き出物は大方がカタログギフトになってはいるが、ちょっと前は確かに結婚式の引き出物にこのような砂糖菓子が入れられていた。
「しかし、何でまた私に?」
犬神は珈琲はブラックで飲む事は殆どの教師、どころか生徒にまで知れ渡っている。
例え珈琲が紅茶になろうがその嗜好は変わらない。
「あら、私てっきり嗜好がお変わりになって砂糖派になったんだとばかり思ってましたけど……。」
「また何でそう思ったんです?」
「だって犬神先生、この間給湯室からお砂糖ごっそり持っていかれたでしょう?」
女性職員の発言を聞いて、犬神は改めて女性の恐ろしさを実感したような気がした。
確かに先日、給湯室から砂糖を一掴みして生物準備室に持っていったことがあったのだ。その時は新月の時期と重なったとはいえ、まさかこの女性職員に見られているとは思わなかったのだ。
「ええ、まあ……確かに。持っていきましたが……」
犬神がバツの悪そうな顔をしながら言葉に詰まっていると、女性職員は何やら一人で勝手に納得がいったらしく、くすくすと笑い出した。
「いやだ先生。もしかして甘党になったのが恥ずかしいんですか?でも別に恥ずかしがる事でもないんですよ。私の主人も昔は全然甘いもの苦手だったのに最近になって急に甘党になっちゃって、今じゃあ糖尿病になりゃあしないか心配なくらいですから。」
「いやそういう訳では……」
「まあ先生が恥ずかしいと仰るならこの事は黙っておきますね。紅茶、冷めないうちにどうぞ。」
一人で勝手に喋り一人で納得してしまった女性職員は、砂糖菓子を犬神の前に置いてさっさと職員室を出て行ってしまった。
これで明日になれば犬神が甘党になったという噂は隅から隅まで広まっている事だろう。
その事に頭を悩ませながら犬神は目の前の砂糖菓子を摘み上げて眺めた。
小さな薔薇の花を模した砂糖菓子は昔のように毒々しい色ではなく、淡いピンク色をしていた。
そしてその小さな花を見て頭に浮かんだのは、甘党と誤解されて他の教員や生徒にからかわれる自分ではなく、この砂糖菓子を受け取ってほんのりと頬を緩めて嬉しそうに笑う、甘党の顔だった。