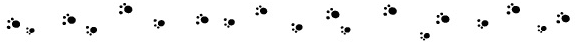▼3
あいつと出会ってから、それほどの月日はたってない。季節はずれの転校生はそれだけで目立ったけれども、それ以上に一目を惹く容姿をしていたから、クラスの女子どもは大騒ぎしていた。
それを鼻にかけない、いい奴だ。
あいつと出会ってから、それほどの月日はたってない。
それでも俺たちはすぐに友達になり、俺が自称しているだけだが親友になった。
側にいて全然苦にならない存在。
だからなのか、何時の間にか、俺があいつの中での「一番」になっているものだと、勘違いしていた。
それは本当に子供じみた感情だけど、確かに俺はそんな感情を持っていたんだ。
あの時、それを嫌でも自覚した。
ただそれだけなのだが、俺にはちょっとショックだった。
高校教師 親友
その日も俺は、放課後にひーちゃんをラーメン屋に誘った。それは半ば習慣じみた事だった。
「おーいひーちゃん、帰りにラーメン食いに行こうぜ。」
「ええ、またかよ。たまには違うもの食べたいよ京一。」
口調は呆れながらも、顔は朗らかな笑顔で俺を迎えてくれた。
この顔は「いいよ。」の前合図。
「いいじゃねーか。あそこのラーメン美味いしさ。」
「分かったよ。じゃあ京一の奢りで。」
「何でそうなるんだよッ!」
軽口を叩きあいながら俺達は他のメンバーも誘う。
「ごめんなさい。今日は生徒会の会合があるの。だから私は遠慮するわ。」
そう言って美里は最後まで謝りながら教室を後にした。
「京一のおごりはすごーく魅力的だけど」
小蒔は勝手に「俺の奢り」と決め付けている。冗談じゃねえ。
「おい、何で俺のおごりになってんだよ。」
「ごめんね、これから部活の後輩と約束があるんだ。だから今日はいけない。また奢ってね。」
珍しく小蒔が「寄り道」の誘いを断った。明日雪でも降るかもしれない。
とすると最後の一人も……?まさかなあ……。
「すまんな。俺はこれからバイトに行かなきゃいかんのだ。だから他の奴らといってくれ。」
最後に誘った醍醐も撃沈した。こういう日は珍しい。
「しゃーねーな、二人で行こうぜ。」
表面上は至極残念そうに振舞ったが、けど内心はちょっとだけ高揚している。
ひーちゃんと二人きりでラーメン屋に行く。
男二人で情けないと思う反面、何故か残念と思うよりもうきうきするような、心が跳ねるようなちょっとだけくすぐったい感情が俺の中に生まれる。
「そだね…。と、その前に行くところがあるんだけど、京一ちょっとだけ付き合ってくれる?」
「いいけど、どこだ?」
その時ひーちゃんがにやりと意地悪く笑った。
悪い、予感がした。
「おー、すまんな緋勇。」
もうもうと立ち込める煙。
目に染みるほどの煙草のヤニ臭さ。
「先生、少し煙草控えたほうが健康にいいですよー。」
「俺はいたって健康だ。あとこれも頼む。」
「先生、ホチキスの歯が無いんですけど……」
「そこら辺にある。」
「そこら辺ってどこですか……」
ぱちぱちとプリントを手際よく止めていくひーちゃん。
「蓬莱寺もすまんな。こんなことにつき合わせて。」
「う、うるせー、俺はひーちゃんを手伝ってんだよ。」
ちょっと寄る所。
まさかそれが俺の最大最悪の天敵の根城とは、思いも寄らなかった。
この部屋の前に来た時点で、断ればよかったんだ。
だけど、二人きりでラーメン屋に行く。そのどうでもいいような日常が堪らなく魅力的で、そして俺は誘惑に勝つことが出来なかったんだ。
そうだ。
ひーちゃんはラーメン屋に行く気はある。
用事だってそう大した時間を割く用ではないはずだ。
だからちょっとだけ我慢してればすぐにこの部屋と部屋の主ともおさらばだ。
「それよりも何でこんなになるまでプリント溜めるんですか。そのつど纏めて置けば楽でしょうに。」
「俺はこういう細々した仕事は大嫌いなんだ。」
「そんな胸を張って言われても……。」
何気ない会話を続ける犬神とひーちゃん。
でもたったそれだけの事が、それだけの事で俺の中はぐちゃぐちゃに掻き回されてしまった。
いつの間にか、俺の知らない間に二人の距離がこんなにも近くなっている。
その雰囲気に俺は居た堪れなくなって部屋を飛び出してしまったんだ。
「あ、京一!」
「……もうあとは俺一人で出来るから、行ってやれ。」
「……はい、じゃあ先生、さよなら。」
「ああ、」
次数制限の都合により続きます……