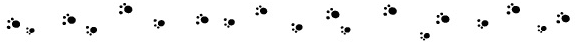▼14
修学旅行最終日。その日、生徒たちは半日自由行動が許され、家族や友人へのお土産を買おうと浮き足立った空気が朝から流れていた。
だがそんな中、緋勇は熱を出して皆と一緒に行動できなくなってしまった。
「ひーちゃん、大丈夫か?」
熱のせいで朦朧とした意識に、心配そうな顔で緋勇の顔を覗く蓬莱寺の顔があった。
「うん、大丈夫だから……京一達は楽しんでよ。」
喉も熱の為にしゃがれた声でしか対応できない自分に、緋勇は少し情けない気分になり涙腺が緩みそうになる。
「でも……何だったら俺このまま側に居るぞ。京都なんて、いつでも来れるしさ。」
その言葉は、緋勇の友人達の言葉そのものだった。
流石に病人の部屋へ大人数押しかけるのは憚られたので、代表として蓬莱寺が見舞いに来たのだ。
「駄目だよ。高校の修学旅行は一度しかないんだよ。楽しまなくちゃ。だけど、寂しくなったらケータイに電話、してもいい?」
「おう!いつでもかけてこいよ。」
その返事を受け緋勇は枕もとに置いてあった自分の荷物を取ろうと、半身を起こそうとしたので、蓬莱寺が先を制して緋勇の荷物から彼のケータイを取り出した。
ふと、そのケータイにぶら下がっているものに、蓬莱寺が目を留めた。
普段、緋勇が付けている携帯電話に付属されている味気ないストラップではない。
そこには今にも飛び跳ねそうな、真っ白な兎のストラップ。
「ひーちゃん、これ……」
「あ、うん。昨日祇園のお店で、買ったんだ。その、変、かな?可愛くて気に入っちゃって……」
ほんの少しだけ、蓬莱寺に嘘をついている罪悪感が緋勇の胸によぎったが、犬神との約束でもあるので、心中で蓬莱寺に謝りながら話を合わせた。
「そんな事ないぜ。まあなんつうか、ひーちゃんにそっくりだなあと……」
その言葉に緋勇は眉根を寄せた。
「……俺うさぎなの〜?」
「あははは、わりいわりい。まあそろそろ時間だし、退散するわ。じゃ、また後でな。お土産、お前の分もしこたま買い込んどいてやるぜ。」
「うん。」
そう言って蓬莱寺と分かれた後、少し話し疲れたのか、一気に睡魔が襲い緋勇は浅い寝息を立て始めた。
熱を出した緋勇の処遇については、とりあえずそのまま旅館で休み、具合が回復すれば駅で皆と合流するという事になった。
そして、教師の一人が旅館に残り様子を見ることになったのだが、その面倒をみるという教師は犬神になった。
養護の教員か、担任のマリアが残るべきだったのだが、他大勢の生徒が怪我や病気を併発しない訳ではないし、担任のマリアは女性であり緋勇は男だ。
その辺りを配慮した他教師から、そして面倒ごとを押し付ける形で犬神にその任が回った。
そして病人の部屋で煙草を吸うわけにもいかず、僅かに口寂しさを覚えながら犬神は緋勇の寝ている部屋へと向かった。
襖を開けると、そこには小さな寝息を立てて寝ている緋勇の姿が目に入った。
そして室内に入った犬神の気配に、緋勇が目を覚ましたのを見計らい、犬神は声をかけた。
「どうだ?気分は良くなったか?」
「せんせい……」
部屋に入ってきた犬神の手には、水の入ったペットボトルと替えの水枕があった。
「ほら、替えの水枕を貰ってきた。頭をあげろ。」
犬神は緋勇の頭を支えながら、水枕を替える。
ついでに額に乗っていたタオルを替えた。
すっかり緋勇の熱で温くなったそれを、犬神は近くにあった桶の水で冷やし清める。
「……すいません。俺の為に迷惑かけて……」
喉が痛むのか、か細い声も枯れていた。
「気にするな。どうせ小学生のようにはしゃぎすぎたんだろう。熱ぐらい出るさ。」
犬神の言葉に「そんなにはしゃいでませんよう……」と笑いながら反論するも、途中で昨日のことを思い出したのか、顔の半分を布団にもぐりこませてしまった。
「その……昨日は、すいませんでした。」
その言葉に犬神は緋勇に顔を向ける。
「ん?ああ、まあな。反省しているのならもう何も言わんさ。それにお前がどちらかというと巻き込まれた方だろう。蓬莱寺もお前と同じくらいに反省していればいいんだがな……。」
深いため息と共に愚痴る犬神を見て、緋勇は自然と笑いがこみ上がったが、途端に咳き込んでしまった。
「ほら無理するな。今日一日は残念だが、おとなしくしているんだな。熱が下がりそうだったら、少し無理をさせるが駅で皆と合流できるさ。」
「……はい。」
そう言って犬神はタオルをどけて、緋勇の額にその大きな掌を押し付け熱を測る。
その犬神の所作に、緋勇はますます顔が赤くなるのを自覚していたが、元から熱で顔が赤くなっているので犬神には気取られずに済んだ。
そして犬神が手を引いたと同時に、緋勇は布団を持ち上げて顔を隠した。
「少し、寝ます。」
「そうだな。水、枕もとに置いておくから。」
「……はい。」
「何かあったら、フロントに電話しろ。俺もそこにいる。」
そう言って立ち去ろうとする犬神の背に、緋勇は枕元に置いてあった携帯電話を取り声をかけた。
「せんせい。」
「何だ?」
犬神が振り返えると、目だけを布団から出して携帯電話に付けてある例の兎のストラップをひらひらとさせていた。
「これ、ありがとうございました。」
そう言った緋勇の、熱の為にうっすらと紅に染まった目尻と、柔らかく犬神を見つめる目に一瞬見とれた自分に驚きながらも、彼は上手に動揺を隠して何時ものように振舞う。
「どういたしまして。」
そして犬神は静かに退室した。
暫くして、犬神は緋勇の様子を伺うために再び部屋を訪れた。
犬神が部屋に入ってきても、緋勇が目を覚ますような気配は一向にせず、聞こえてくるであろう寝息も、部屋に置いてある加湿器が蒸気を吐き出す音によってかき消されている。
僅かに上下する胸だけが、緋勇の息遣いを伝えてくる。
犬神は緋勇を起こさぬようそっと窓際にあるソファーに座り、暫く様子を見ていた。
だが、緋勇が額に乗せていたタオルが落ちているのに気が付き直してやろうと、立ち上がり緋勇の側に膝を付いた。
しかし近づいて手に触れたのはタオルではなく、幾分か熱の下がった、緋勇の額だった。
そしてそのまま真っ黒なくせっ毛を優しく梳いてみる。
汗で少しばかり湿った髪の毛は、するりと犬神の指を通り落ちた。
そして指は導かれるように、目元を、頬を、乾いた唇を触れていった。
自分の行動に驚きながらも、その予想以上に心地良い緋勇の感触に抗い難く、更に上下する白い喉に触れようとした。
途端、目に入ったのは、緋勇の手が握っている携帯電話に付けらた、兎のストラップ。
その兎は、まるで自分を責めているように、そして監視しているように犬神にその赤い目を向けていたのだ。
「……馬鹿なことだ。」
その赤い目に、犬神は我にかえったようにそう呟くと、落ちていたタオルを緋勇の額に当てそのまま部屋を出て行った。