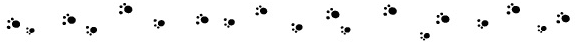▼11
ぱたん、と少し毛羽んだ書物を閉じた彼は、やがて庭に目を移し咲き誇る桜の木を見つめた。暫くすると、水干を着た美しい女房が白湯を運び恭しく彼に差し出した。
「ありがとう、芙蓉。」
労いの言葉をかけると、芙蓉、と呼ばれた女房はそのまま主の視線を追い、庭の桜の木に目を移した。
「桜を、見ておいででしたか?」
一口、芙蓉の運んできた白湯を含むと、息を吐きながら無言で頷いた。
「あの事件から、随分と年月が経ったのだと、思っていたのだよ。」
そう言うと、芙蓉の主は手元の本に視線を戻した。
本、といっても紙を簡単に纏めた小冊子のようなもので、これは宮廷で起きたある事件の詳細を記した数少ない資料の一つだ。
主の言葉を聞きながら、芙蓉は少しばかり顔を顰めて桜の木を眺め続けた。
その表情に主が気付き、声をかける。
「芙蓉は、もちろんその事件の事を知っているでしょう?私よりも長くこの宮中に居たのですから。」
「すいません。」
自分を責めていると勘違いしたらしい芙蓉は、表情の乏しい身ではあるが、感情が無いわけではない。
その表情を見て主が慌てて言い添えた。
「ああ、お前を責めているわけではないのだよ。あの頃まだお前は主を決めていなかったのだから手を出せずにいたのだろう。それに、例えお前が自由になっていたとしてもだ、この事件を防ぐことは出来なかっただろう。」
「それは、相手の力があまりにも強大だったからでしょうか?」
そのどこか幼い質問に、主はふっと、悲しげな表情で笑いながら芙蓉に話し掛けた。
「違うのだよ。起こるべくして起こった、鬼は、生まれるべくして生まれたからだよ。」
そうして、幼い頃の記憶を呼び起こす。
どこか儚げで、それでいてあまりにも美しかった、あの方。
ただの陰陽師見習の子供にも、優しく接してくれたあの柔らかな手。
それが消えてしまったあの時の、自分の感情。
「ああ、さぞ美しく、咲いたのであろうなあ……。」
その呟きは、薄紅色の霞に吸い込まれていく。