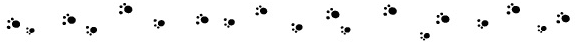▼10
幼い頃から誉めそやされていた。その利発さが、その容姿が、その心根が、かくも神童のようだと周囲が誉めてくれた。
あまりにも幼かった故に、誉められる言葉の意味も深く知っているわけではなかった。
ただ、ただ自分がありのままに振舞うと、周囲の人々や父が誉めてくれたのだ。
そして何より、私が誉められると母が喜んでくれる。
それが一番何より嬉しかったのだ。
ただ……
無邪気な子供時代は過ぎてある程度知恵が付き、幸か不幸か、私は人よりも聡かったのだろう。
だから余計に、すでに東宮の地位にあった兄の愚鈍さが、目に付いた。
一瞬でも、そう思ったら私の心は闇に染まる。
だから、そう思った自分を封じた。
心の奥底に、誰にも見られないように、触れられないように、自分自身ですらその闇に目を閉じ耳を封じておいたのに……。
このところ続いた内裏の警備の強化のせいで、働き詰であった臣下たちの労を労うために、久しぶりに華やかな宴がもようされた。
もちろん本当のところは、宮中で起こっている件の怪異事件が一向に解決の色を見せないでいる為に、周囲に当り散らす帝の気を静めるために両大臣達が整えたものだった。
今を盛りとばかりに権勢を振るう両大臣が整えた宴だけあって、これまでに類を見ないほどの華やかで、そして豪華な宴に帝も満足しているらしく、珍しく弁が軽やかになり、そして杯を開ける進みも速くなっていた。
「のう、これほどの宴に、珍しき花も無いとはいささか無粋とは思わぬか?緋勇。」
突然自分を呼んだ帝に、どこか遠くをぼんやりと見ていた緋勇は慌てて御簾越しの帝を仰ぎ見た。
「恐れながら、珍しき花といえなくも、今の季節を盛りにとこれほど見事に咲き誇る桜が皆の目を楽しませておりまする。」
そう言いながら緋勇はきっちりと調えられた庭に咲き誇る桜を示したのだが、その答えに帝は既に酔っているのか、ころころと大声を上げて笑った。
「相変わらず硬いのう、緋勇。珍しき花とは文字通りの花では無いぞ。ここに集い競うように美しく咲き誇る花たちがおるではないか。」
そう言って帝は家臣たちに酒を振舞って回る女房達を指し示した。
「はあ、これは無粋な事を申しました……。」
恭しく頭を下げる緋勇を満足げに眺めていた帝はぼそりと呟いた。
「花が、風に舞う姿はさぞかし美しかろう。誰かに舞わせよ。」
その帝の言葉に女房達の顔がさっと引きつった。
無理も無い話である。
女房という身分であろうとも、ここで直接大臣達の世話をしている女房達は元々は良家の子女達がほとんどだ。
やんごとない血筋の姫君も中にはいる。その姫君達に、あろうことか皆の前で白拍子の如く舞えというのだ。
これはとんでもない辱めに等しい。
「恐れながら……」
と進み出た左大臣の言を帝はきつい視線で黙らせた。
管弦の樂も、ひそひそと話される臣下達の囁きも、一瞬この場から消えうせた。
その沈黙を噛み締めるように、緋勇は床に置いた手をぎゅっと握りしめた。
そして面を上げた緋勇の顔は、今までに見たこともなように美しく微笑していたのだ。
「帝……、花、とはいえませぬが、珍しきものを、お見せしましょう。今はそれでご勘弁を。」
そう言うと、緋勇は一旦宴の席を立った。
緋勇が宴席から席を外してからほんの数刻。
宴席に現れたのは剣を腰に挿し、烏帽子を被り水干を纏った白拍子だった。
扇で顔を隠しながらしずしずと宴席の中央へと進み出ると、静かにその扇を閉じた。
現れたその顔に、どよめきと感嘆の声が宴席を支配した。
帝はただ狂ったように笑い、手を打ち白拍子に身をやつした緋勇の姿を絶賛した。
「主上、男が舞う女舞、珍しく滑稽な舞をご覧下さい。」
そう静かに口上を述べると、緋勇は鼓の音に合わせ扇舞を舞い始めた……。
後に語る者が言うには、それはまるで夢の如き宴だったという。
あの晩の出来事は、その場にいた僅かな殿上人の目に焼き付いている。
薄く紅をひいた緋勇朝臣の白い面は、青白い月の光に照り返り、桃源郷の乙女が目の前で舞っている様だったという。
桜の花びらが闇の中薄紅に光り、扇が翻るごとに花びらは緋勇の周囲を舞い、その幽玄の姿は今でも目の前に焼きついてると、大臣の一人は語った。
その舞の中、天子の背後に迫る真っ赤な狼が、天子の喉笛を食い千切る様を、誰一人動かず呆然と眺めていたのは、その舞に魅せられていたからだろう。
そして緋勇も、一瞬の内に繰り広げられた惨劇に気づきながらも舞を止めることなく、動かずに静かにその帝の血に濡れていく姿を見守っていたのだという。
ただ真っ黒な瞳から止め処も無く涙を流しながら。
そして赤い狼が、天子の肉を満足げに食らう様を見届けると、桜に庭に降り立ち、そこにいつの間にか佇んでいた青い狼の背に自ら乗ると、青い狼はそのまま緋勇を連れて何処かへと去っていってしまった。
後に残ったものは、ただ呆然となる殿上人。
そして天子の肉を食らい満足げに息を引き取った、赤い狼。
それから……
鈴が転がるような、どこか気の触れた笑い声の木霊が、いつまでも桜闇夜に残っていた。