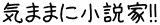ボム・メール Letter 5 -Last Letter-
ボム・メール Letter 5 -Last Letter-「ああ、気が付いたの……」
ベッドの左側に、椅子に座ってこちらを見つめている母親がいた。どうやらあれこれと世話をしてくれていたらしい。
「あなたね、横断歩道の真ん中で急にうずくまって、その瞬間に車にぶつかったの。すぐにパトロールしていた横山さんが救急車を呼んでくれてね。うちに電話してくれたのよ。ぶつかっただけだったから、大した怪我はしていないけど……先生が、まだ精密検査があるから入院しなさいって」
わたしは黙ってうなずいた。喉がひどくかわいていて、声を出すのが辛かったのだ。
「病気なの、わたし?」
ささやくようにきくと、お母さんはゆっくり首をふった。
「特に病気のような症状はないし、大丈夫だろうって」
てっきり、不安と恐怖で心臓発作を起こして死んでしまうのだと思っていた。今生きているということは、心臓に何か病気があったのかと思ったりもしたのだ。
「ねぇ……。お母さんは、悪魔を信じる?」
わたしは不意にボム・メールのことを思い出した。
悪魔なんているはずないじゃないの。そういう優しいお母さんの声がききたくて、わたしは無邪気にたずねていた。
「信じるわ」
間髪入れずに答えが返ってきた。
それは、間違いなくお母さんの声だった……。
「悪魔はね、人の形になれなかった人間だと思うの。だから、悪魔は人間に対してイタズラをしかけてくるんだと思う。それがきっと、今回のようなあなたの不幸になるのよ」
お母さんは、わたしを諭すように、落ち着かせるように言った。
「そして、ボム・メールも……」
「今……何て?」
娘はひどく驚いた様子だった。
「ボム・メールはね。お母さんが作ったの」
娘の丸い目がわたしに何かを訴えかける。だが、わたしは何もいえない。
「偽名を使ってボム・メールを書いて、お隣の内場さんに出したの。わたしの名前には"A"が入っているし、内場さんなら"B"がはっているでしょ。本当に、思いついたときはイタズラだったの」
四ヶ月前、隣に引っ越してきた内場紀子は、わたしが大学生だったときの美術部の後輩だった。才能のあった紀子は、優秀だったわたしを出し抜いて、県で金賞を受賞した。紀子のことは褒めてあげたし、紀子もわたしの絵を褒めてくれた。
やがてわたしは退部し、紀子は部長になった。名残として、わたしたちの絵は部室の前に飾られた。だが退部して数日後、わたしの絵は突然部室の前から姿を消した。
その日の放課後、静かに美術部の部屋を覗くと、わたしの絵は部屋の隅に置き捨てられていた。しばらくして、紀子率いる部員たちが絵を袋に入れた。それは紛れもなくゴミ袋だった。
「わたしはあなたを困らせたかったんじゃないの。内場紀子が嫌だっただけ」
けれど、ボム・メールはめぐりめぐって"Y"の番で娘にまわってきた。うちの苗字は吉澤だと、手紙が来たのを知ったときに初めて気がついた。
娘がどうするのか見ていたが、今入院して横たわっている娘をみると、ボム・メールなど内場紀子を苦しめるのには必要なかったのだと思った。
紀子は白い便箋と青い折り紙を見たとき、思い出しただろうか。
真っ白なキャンパスに青い空が描かれ、やがては捨てられた不幸な絵のことを。自分が傷つけた絵と、その作者のことを。
「でもわたし、死にかけたね……」
わたしは病室の空中をぼんやりと見つめ、お母さんから視線を逸らした。それでもお母さんの視線は、わたしに突き刺さっていた。
そんなお母さんが可哀想で、でも何故か嫌だった。
「悪魔のイタズラは絶対だから―― ……」
だけど、わたしは悪魔なんて信じない。悪魔は、人間がイタズラに作り出したものだから。
<終わり>