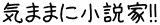短編小説 Going my way
短編小説 Going my way勉強するために学校に行くなんて信じられない。小さい頃から人としゃべるのが好きだったから、小学校でも、廊下を歩けば数十人の友達と目があうくらい、多くの友達と一緒だった。
けれど、中学に入ってから、それがすごく恐ろしいことだと思えてならない。彼らが、言葉という恐ろしい武器をもっていることが分かったのである。
言葉で思い知らされる痛みが暴力の痛さよりもひどいということが、携帯電話を持ってメールをし始めてからはじめて知った。
メールのたった数文字が、友達という関係を断ち切ってしまったことも、その関係を回復させたことも、ここ半年で何度かあった。
携帯電話の着信音が鳴るたびに怖い。誰からのメールだろう。内容は自分を傷つけないだろうか。
毎回おびえる。そんな必要は全くないのに、反射的にボタンを押して着信音を止めてしまう。そして、心臓のバクバクする音を聞きながら、メールを開封。
その繰り返しに、自分は弱いかなあと思って、むなしくなるのだ。
「自分らしく生きたらいい」
「何か夢はないのか?夢があれば幸せに生きられる」
「なんとかなるよ。悩んでいたことなんて今に忘れるよ」
大人だけじゃない、見知らぬ誰かのアドバイスはそんな言葉しかない。結局、一時の気休めにしかならない言葉だけがある。
それで解決するのなんてごく少数の人間だけじゃないか?
その言葉が現実に役立つことがあるか?
現実に歯向かえず、でも気休めの言葉を信じようとする自分は、やっぱり弱いんだろうなと思えてならないのだ。
そうした生活の中でも、やはり勝手な人間はいる。こちらが悩んでいるとも知らないで、こちらをいらだたせる奴がいる。
でも、自分が怒っていると、相手が何を考えて何を悩んでいるかなんてかまっていられなくなるのが現実だ。
学校の廊下ですれ違うたびに目線がまじわり、うらみやいらだちや怒りが交差する。それが嫌で目線をそらすことも、それに等しく心の負担になる。
今起こっているその相手は、本当に身勝手としかいいようがない。
女子は新しいクラスになって一学期もすると、属するグループを変えるやつが数人は出てくるものだとうすうす知っていたつもりだった。しかし、男子も案外ひとまとまりに見えても、そうでないこともある。
実際悩んでいる俺がそうだ。クラスでも、リーダー格という暗黙の了解を得ているやつがいて、そいつとは小学校の時から親しくしていたけど、しつこく遊びに誘ってきたと思えば、自分の都合でそれをやめたりする態度にうんざりしている。結局遊び相手が欲しいだけで、過去の自分と一緒だからだ。
そいつと縁を切るのは簡単である。
相手が自分勝手でも、こちらが遠慮する必要なんてないと最近気付いた。そういう奴は、こちらが遠慮しているのさえ気付かないのだから。自分だって、自分のしたいとおりに生きていかないと駄目なこともある。
Going my way.
その言葉がこの世になければ、俺はいつまでたっても強がるままだった。