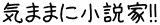短編小説 シリトリ
短編小説 シリトリ僕は、自分が手を引いている小さな妹によびかけた。彼女の名前は、葉月という。今年小学校に入ったから、僕とは二年違いだ。
「しりとりしようか」
そう提案すると、真っ赤な新品のランドセルを背負った葉月は、にっこりと笑ってうなずいた。
母が入院して一ヶ月。病院にお見舞いに行くごとに、葉月の言葉遣いや気遣いはしっかりしてきている。小さな責任感を背負う妹に、何か兄妹らしき遊びをしてみようと、とっさに思いついたのだった。
「りんご」と葉月が始めた。
「ごりら」僕はスムーズに口を動かす。
「ランドセル」
葉月は自分のランドセルを得意げに指差す。ラッパと言うのかと思ったのに、ちょっとおどろいた。
「ルーレット」
「トンネル」
葉月は本を読むのが好きだ。語彙もたくさんあるのだろう。
「ルビー」
「ビ……? あっ、ビール」
「ルばっかりじゃないかよ」
自分で提案しておきながら、かなりあせっていた。妹に負けたとなれば、笑いのタネにされるのは確実だった。
「ルーペ」
理科の授業に出てきたので、使った。案の定妹はルーペというのを知らなかったので、虫眼鏡のことだと説明した。
「ペンダント」
「トースト」
なるべく小学校一年生の女の子に分かりやすい言葉を選ぶ。兄妹なのに大変だよな、と、ひとり愚痴る。
「と……、とーこーきょひ!」
とーこーきょひ。
妹の言葉は、ためらうことなく僕の頭の中で変換された。登校拒否。
「どうしてそんな言葉知ってるんだよ」
僕は怒るつもりだった。妹は、長いこと幼稚園に来ていなかった同じクラスの子について、母親達が「かなり早い登校拒否かもねぇ」と言っていたのをきいたと説明した。
「意味、知ってるのか?」
僕が聞くと、妹は首をかしげて「よく分からない」と言った。そこで、僕は安心した。このしりとり、終わらせた方がいいなと直感的に判断した。
「じゃ、つづきな。ひ、だから……ひみつ」
「ひみつ?……つ? んーと……、つくし」
「しまうま」
「マント」
それから、無難なしりとりが続いた。僕は正直安堵していた。
妹が「かるた」と言ったので、僕が「タクシー」と言ったときだった。
「し……、しぼう」
しぼう。
その言葉がなかなか頭の中で変換されなかった。頭の中にうずまいていたのは、母親のことだった。急に仕事中に倒れてから一ヶ月。病名はまだ聞かされていない。だが、これまで僕が見ている限り、体力はあまり回復しているとはいえなかった。
そんな母親が、仕事を休んで見舞いに来た父親にこう言ったことがある。
「外でカロリーの高いものを食べているのね。お腹に脂肪がついてきたわよ」
ダイエットしなきゃね、と言って笑っていた。
脂肪か、あるいは―― 死亡。
母の様子から、子供特有の直感を葉月が働かせていたのだとしたら。そう思うと、僕は怖くて怖くて、続きを言うことができなかった。
「お兄ちゃん、今から塾?」
僕は夕飯を食べながら無言でうなずいた。今日から、通っている進学塾の夏期講習会が始まる。小学六年生になって中学受験生となった僕の毎日はかなり忙しく、近頃はあまり葉月ともしゃべっていなかった。
「それにしても受験生なんてねぇ。今時の小学生は大変だわ」
一年前に退院した母がそうつぶやくと、葉月はふふっと笑った。
「お兄ちゃんの志望校がレベル高いから、とびきり大変なのよ」
「しぼう」こう。その言葉に思わず三年前の記憶がよみがえる。
母親は元気だ。父親も健在だ。妹も大きな病気ひとつせず、今は小学三年生だ。僕も、忙しいながらも毎日楽しい。
「行ってきます」
一言声をかけて、家を出る。
僕はあれから、妹に何一つきけなかった。
小さな妹が、この世のおそろしいものやこわいものをどれだけ知っているのか、分からない。でも、何かを知っている気がする。こわくておそろしいものを、自分よりもはるかに多く知っている気がする。
そんな思いをむりやり消し去るように、僕は蒸し暑い空気の中、自転車のペダルに足をかけた。