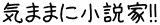短編小説 空の中に、太陽がひとつ
短編小説 空の中に、太陽がひとつため息もでるくらいに。元が何色かも忘れてしまうぐらいに。
私はよれよれの靴をつっかけた。うちにこんな靴があったんだなぁと思いつつ。
アクリル絵の具をたっぷり染み込んで、服は重かった。
立ち上がると、体の節々が痛んだ。弱った関節に、体重が辛い。
おぼつかない足取りが、それを語っていた。
自分の手を眺める。しわだらけの手の甲。細い指。小刻みに震えて、絵の具に染まった汚い指先。
美しいものを作り出す際に、どんどん自分が汚くなることが、私にはどうにも愉快だ。
足もきっと弱ってきている。白いひげものびっぱなしだった。
外の世界は腐っていないだろうか。まだ太陽は輝いているのだろうか。
病人ではないのに、病人になったつもりで、分厚いカーテンを開けた。
おぼつかない足どりで、よれよれの靴を履いた。こんな靴がうちにあったんだなぁと思いながら。
外の鳥はさえずりを奏でているのだろうか。風は季節の匂いを運んでいるのだろうか。四季折々のひとつひとつが、毎日芽吹いていることと信じたかった。
私は何も変わっていない。そのことを、四季の移り変わりから感じ取りたかったのだ。
太陽はまだ輝いていた。老年の体には、太陽のきつい光というのはどうにも辛い。
空はまだ青かった。水色とも、アクアマリンともいえない。どの青色の絵の具を混ぜても足りないくらいに深くて鮮やかな色だ。きっとこの色は出ない。何をしても、この色にはならない。
私のか細く開いた目に、日光は絶え間なくそそがれる。少し刺激が強すぎかもしれない。
太陽の色もまた、何色でもない。黄色には近いが、近くで見ると赤なのだと教わった。手にこぼれ落ちてくる光は、何の色もまとっていないのだから、無色とも言える。だが、太陽は色があって初めて見える。空の中に、太陽が見える。
太陽は色をまとわない。だからひとつしかないのだ。あの色は、いや宇宙中でたったひとつしか完成しない、特別な色なのだ。
太陽がひとつだから、太陽なのだ。
そこまでして、とくとくと胸騒ぎがした。興奮とも言い難い、もどかしい動きを心臓が繰り返す。いや違う、動いているのは心かもしれぬ。
「絵などまだまだ無力なのだな」
おぼつかない足取りで部屋に戻る。
部屋には、私と空気しか住んでいない。
半年近くかけて命がけで完成させた絵を、私はためらいなく、赤い絵の具で汚し始めた。