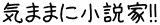短編小説 わたしと赤と青と
短編小説 わたしと赤と青と都会の生活ときれいなキャンパスに憧れて入学したこの大学も、今ではすっかりおなじみで、緊張感のかけらも無い。オープンキャンパスのときに、正門をくぐるだけで息が詰まるほどわくわくしたあの感触は、二度と戻ってはこない。
夏には暑い暑いといいながら半袖の服をパタパタしていた自分が、今はこうしてマフラーと手袋に包まれているなんて、毎年のことだけど信じられない。
春に始まった大学生活は刻々と時を刻んでゆき、わたしをクリスマスの前日まで見届けてくれた。
勉強もサークルもバイトも、がんばっているんだけどそこそこの結果。
大胆な人間になりたいけれど、小心者の自分。
それを隠そうとして必死な毎日。でもなぜか楽しかった。
同じ授業をとっている古西くんという人がいた。
わたしは彼のことを、予備校時代から知っていた。同じクラスだったのだ。
話を小耳に挟むと、とても面白い人みたい。
けれど、高校も違えば接点もないし、話すきっかけがない。
大胆になりたいのはそのせいだ。
古西くんの隣の席に自然と座って、写メを見せ合い笑い転げている女の子たちが、正直うらやましかったりもした。
あの当時、「自然に話しかけられるテクニック」という本があったら、買っていたと思う。
いつものように講義が始まる。心理学系の授業で、わたしは興味があってとっている。彼が友達と話すのを聞いていると、穴埋め程度に来ているというので、ちょっとがっかりしている。
それでも、最前列に座る彼。彼はとても愛おしく見えた。
わたしはいつも一人で前から5列目の席に座っている。
ここは黒板と古西くんが一目で見える、誰にも秘密の特等席なのだ。
今日の内容は説明が分かりやすくて、わりと面白かった。
講義が終わる。
古西くんはペンケースをしまうと、そそくさと出て行く。行き先はおそらく、時間的にサークルだ。
教室を出ようとすると、先生に呼び止められ、
「お前、古西のとこへ行ってこい」
「えっ。なんでですか?」
彼の名前が出て、心の中では焦りまくり。でも、わたしの声はあまりにも冷静。
「理由はあいつに聞けば分かる。ちゃんと説明してあるから、早く行け」
わたしはとりあえずおじぎをした。すぐに教室を飛び出した。
冷静だった心臓が、だんだん早くなり、わたしを駆け足にさせた。
なんで、気付かなかったんだろう。
どうして、もっと早くに彼に一言話さなかったんだろう。
わたしがときめいていた生活を、送らなかったんだ!
教室のある棟の出入り口を出たところに、古西くんが歩いていた。
何も言わずに古西くんのカバンをつかむと、当然だけど、彼は驚いてこちらを振り向いた。それでも、何も言い出さない。
「おれ、クラブあるんだけど」
確かにそうなのだ。でも、わたしは言った。
「ちょっと話さない?」
彼は、マフラーの中に顔をうずめて黙ってこちらを見てきた。
わたしは数秒後に、もう一度言った。
「ごめん。クラブ行かないとダメだしね」
彼はまた何も言わずに去ろうとしたけれど、わたしが手を振ると、
「また今度」と口を開いた。
嬉しいのと不思議なのとで、わたしはそのまま校門を出た。
息を吐くと、それは白く輝いた。
街灯に、電飾で飾られたクリスマスツリーが並んでいた。
おさえていた気持ちと、今までの気持ちが、わたしの中でようやくひとつになった。