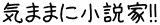その少年は、終幕を告げる その少年は、運命を変える
その少年は、終幕を告げる その少年は、運命を変える黒髪と顔立ちを見ると、日本人らしい。だが、彼は何となく日本人にない雰囲気をまとっていた。
原沢は立ちすくんだままだった。何もしなかったし、何もしゃべらなかった。少年に「早く帰れ」と注意もしないし、優子に「早く帰ろう」ともうながさない。
この人には、本当に子供を見る目があるのだろうか――?優子は、ときどき不思議に思い、戸惑う。
原沢は感情を表に出さない人物である。滅多に笑わない。それゆえ、孤独のオーラをまとっているようにも思える。だが、無駄に知識が多い。本人に言わせれば、先天的に勘と記憶力がずばぬけているのだというが、確かにそうかもしれない。授業中に教えてくれる予備知識の量は半端ではないし、そのおかげで優子は原沢に興味をもった。
原沢は、ときどきこうこぼす。
「僕は、教師には向いてないんだ」
そう、優子自身もときたまそう思う。原沢はあまりにも無感情だ。多感な子供にとっては、見ていても面白くもなんともない。人間性をつちかえとか、積極性を持てと原沢に言われても、納得する者は少ないだろう。でも、授業は他の教師よりも面白い。決して笑いだけで勝ちとれるものではない信頼感をえている。
教師という職種ではなく、誰かのそばにいる―― そういう人物に向いているのだろう。それをあっさりと認めてしまう、原沢のサラサラした性格が、優子はとても好きだ。
しかし、今回の場合では、原沢は対応できないようだった。現状を飲み込めていないらしい。それは優子も同じだったのだが、少年がこちらを食い入るように見つめている今、ゲームセンターのことや喫茶店のことなど、どうでもよくなっていた。
「どこかで会いましたっけ?」
少年は、それに答える代わりにいきなり優子の左手をつかんで、グイグイと歩き出した。
引っ張られていく優子を、原沢は慌てて追いかけた。
少年は、優子と原沢が行こうとしていた喫茶店に入ると、「3人、喫煙席で」と言いながら、ウェイターに向かって指を三本つきだした。ウェイターは迷うことなく、店の一番奥にある一段高い喫煙席へと優子たちを案内した。
原沢と優子、それに向かって少年というように座り、水とおしぼりを持ってきたウェイターが遠ざかるのを待った。
「こんなところに連れてきて、何のつもり?君、お金持ってるの」
原沢がイスにふんぞりかえる。少年は姿勢よく座ったまま、口を一文字にとじていた。原沢と優子は顔を見合わせ、仕方なく、オーダーをききにきたウェイターに、アイスコーヒーを3杯注文した。
アイスコーヒーの注文を持ち帰ったウェイターが遠ざかる。それを待っていたように、少年が口を開いた。
「あなたがたに、助けてほしいんです」
は? と優子は思わず声をあげていた。「何を助けてほしいって?」
少年は、ていねいにおしぼりで手を拭きながら、言った。
「世界が終幕へと向かっています。それを止めるのを」
この少年は一体何者なのか。それを、優子は一番にきいた。なぜ、世界が終幕にむかっていると分かるのか。原沢はそれを一番に少年にたずねた。
少年は表情を変えずに、運ばれてきたアイスコーヒーについてきたストローの袋をていねいに破りはじめた。
「あなたがたを巻き込んでしまうことになるのは、申し訳ありません。ここに連れてきたのは、僕の正体を他の人間に不用意に知られないようにするためです」
「喫茶店に来たところで、君は十分目立つけどな」
原沢がアイスコーヒーを乱暴にかきまぜる。多少、いらだっているようだと優子は推測する。
「僕の見た目はどうでもいいんです。僕が気にしているのは、におい」
「におい?」
優子はくんくんと鼻を動かした。少年が自分のにおいを気にしているのだろうかと思ったが、特別変なにおいはしなかった。原沢も首をかしげた。
「僕からは、ある特定の民族の鼻にだけ区別が出来る、特殊なにおいが出ているそうなんですよ。けれど、彼らは煙のにおいの中からだと僕のにおいを探し出すことが出来ない。結果、煙のにおいがきつい喫煙席にいれば、彼らに探し出される心配は少ないんです」
少年は黙ってアイスコーヒーを飲む。原沢は納得しかねない、といった表情だった。
「君は誰かに追われているのか?においをたよりに追われるほど、特殊な人間なのか?まさか、現実世界でゲームをしているんじゃあるまいな」
ゲーマーの原沢は、そこにかみつく。
「僕が関わっているのは、そんなちっぽけなもんじゃない」
少年の目に、力がこもった。原沢が、少し身を引く。優子は無意識の内に、ストローをくわえるのをやめていた。