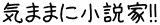その少年は、終幕を告げる その少年は、キーパーソン
その少年は、終幕を告げる その少年は、キーパーソン「なんでアイスコーヒー、俺のおごりなんだよ……」
何百円の出費でも、自炊が下手な原沢は嫌がった。
リクはどこへ向かう気なのか、ただもくもくと歩き続けていた。優子も、家へ帰る気は失せていた。変人教師と突然現れた少年と一晩すごすのも悪くない、と思った。母親だって困りはしないだろう。一人分の食費が浮いたと喜ぶだけだ。
「僕には家がありません」
リクは唐突にしゃべった。
「家と呼べるべき場所を知らないうちに、こんな目に遭ったんです」
それは、辛い運命を背負い、苦しい生活を強いられてきた者の口調だった。
「幼い頃は、曾祖母と二人で太平洋に浮かぶある島で暮らしていました。そこへ、大きなヘリコプターに乗った連中が次々と現れ、島ごと占拠したんです」
日が暮れそうだった。
リクの姿は闇にとけはじめていた。
「連中って、今お前を追っている奴らか」
原沢の問いに、リクは
「そうです」
と答えた。
「彼らの名前は分かりません。特殊な機械を持っていること、その機械は100万人の中からでも僕を探し出せるということ。この二つしか僕の持つ情報はありません」
さらに小一時間歩いたところで、さすがの優子も疲労を感じはじめた。
「ねぇ、どこまで歩くの」
リクに訊ねると、彼は立ち止まって優子を見上げた。
「海です」
そして、ふぅっとひと息ため息をつく。
「海に着くまでが勝負です。海に着くまでに彼らに見つかればアウトです。見つかれば、僕は強制連行されて施設の中で24時間監視され、体中を調べられます」
潮風のにおいがした。東の方向からだ。
「お前、なんかウイルス持ってんのか?」
原沢は低い声でたずねた。
リクは目を伏せて、答えた。
「そうとも言えますね」
「そう、とも?」
リクは唇をかんでいた。必死に涙をこらえていたのだ。
「僕の体に流れる血には、ある成分が普通の人よりも多く含まれています。ヤツラは以前からある植物を栽培していて、その植物からもある成分が取り出せます。このふたつをかけあわせると……」
「ウイルスが出来上がる、ってわけだ」
原沢が言った。
リクは、静かにうなずいた。