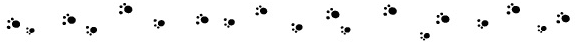▼11
跳ねる兎2「犬神先生。」
その店の暖簾を潜り店内に入れば、そこには予想通りの人物がいた。
「お、何だ緋勇か。」
緋勇の姿に少し驚きながらも、やんわりとした笑顔で犬神は応えた。
「こんな所で、先生に会うとは思いませんでした。」
「はは、変なところを見られたな。」
くすりと笑いながら店内を見渡せば、こじんまりとした店構えながらも、可愛い小物や手の込んだ工芸品が置いてある店で、どうやら知る人ぞ知る、というような店であるようだ。
その証拠に、表通りの賑わいから推し量れば、店内にいる客の数は多くなかった。その数少ない客も、今しがた勘定を終えたらしく次々と店を出て行ってしまい、店内に残ったのは店の主と犬神と緋勇だけとなってしまった。
きょろきょろと店内を見渡す緋勇に、犬神は苦笑を浮かべながらこの店に来た理由を話した。
「ここは、こんな店構えをしているが、割と老舗なんだ。それで修理を頼んでおいたんだ。」
「へえ。修理って、何の修理を頼んだんです?」
そう緋勇に問い掛けられて答えようとした時、店の主人が犬神に小さな小箱を渡したのだ。
「犬神様、こちらですね。」
「ああ、すまんな。」
「いえいえ、こういったもんの修理はお手の物ですから。今後とも御贔屓に。」
「何ですか?それ。」
堪えきれず、緋勇が犬神に話し掛けると、犬神は小さく笑って箱を開け緋勇に見せた。
中には小さな銀細工の、兎がちんまりと座っていた。
「かわいいですね。」
「根付だ。」
「根付?」
「ああ、江戸時代ぐらいに煙草入れなんかにつけて帯に止めるための小道具だ。まあ今でいうストラップみたいなものかな。それを修理に出しておいたんだが、丁度修学旅行中に仕上がるというんで、受け取りに来たんだ。」
そう言いながら犬神は、その兎の銀細工を取り出して緋勇の掌に乗せてやる。
ひんやりとした金属の感触と、小さいながらもずっしりと掌を圧迫する重さ、そして恐らく初めて見るであろう根付という工芸品。それら全てが緋勇には珍しいらしく、じっとその兎に見入っていた。
「へえ、先生、根付を集めるの、趣味なんですか?」
「いや、違う。これは……」
緋勇の言葉に、犬神は少し言いよどみながら言葉を続けた。
「昔、女に貰ったんだ。」
「え?」
跳ね上げるように、緋勇は犬神の顔を仰ぎ見た。
その根付の兎を見つめる犬神の表情に、緋勇の胸に締め付けられるような痛みが走った。
「もう随分昔だがな……。」
そう言いながら、犬神は緋勇の手から兎を摘み取り元の箱に収め、それまで黙って成り行きを見守っていた店主に渡した。
「では、包んで参りますよって、待ってておくれやす。」
そして、店内は本当に二人きりになってしまった。
表通りからの喧騒が僅かにこの店にも聞こえてくるが、それ以上に緋勇は自分の心臓の音が耳障りで仕方が無かった。
何故なら、こんなに早く跳ね打つ音は、初めてだったのだ。
この感覚には覚えがある。
だけど、あの時はまだ幼くて、その言葉も言葉の意味すらも理解していない遠い過去のものだったのだのだ。
自分の心音の変化と、そして犬神がちらりと見せた過去の陰に酷く怯えている自分。
気がつけば、その言葉を発していた。
「その、女の人って、もしかして、恋人?」
何で自分はそんな事を聞いてるんだろう?
そんな分かりきった答えを求めてどうする?
自分の何がそんな言葉を発しているのか分からなかったが、でも一つだけ分かったことがある。
それは、これが確かめる為に発した質問ではないこと。
もしかして否定してくれるのではないか?その愚かな希望が発した言葉だということだった。
「……そうだな。そう言ってもいい、仲だった。」
「その人は、今は?」
「死んだ。」
「!、すいません。」
思わぬ答えに、緋勇は反射的に謝っていた。
「構わんさ。そう、そいつは死んでしまったが、何となくこれは持っている。」
「一途、なんですね。」
多分、一途に、想っているのだろう。
その恋人を。
「はは、一途なんて言葉は若い奴が言われれば可愛いが、こんなおじさんに言われてもなあ……」
「可愛いですよ。」
本当にそう思った。
だから何の疑問も持たずに思わず言葉が漏れてしまった。
「は?」
面食らったように犬神が緋勇の顔を見た。
すると、自分の発した言葉の意味をやっと理解したのだろう。
ほんのりと顔を赤らめ、それでも消え入りそうな声で、しかしはっきりと犬神に言葉を届けた。
「一途なおじさんも、可愛いです。」
「……。」
暫く、声が出せないでいる二人だったが、犬神がその右手を上げようとした時、店主が店の奥から戻り時間が動き出した。
「お待たせして……どうしなはったん?」
きょとんとする店主に、犬神は上げかけた右手をそっと下ろし、代わりに店内をぐるりと見渡しながら俯く緋勇に話し掛けた。
「……せっかくだ。何か記念に買ってやろう。」
「え?」
「どれがいい?まあ半分口止め料だ。蓬莱寺辺りに知れればからかわれるのが落ちだからな。」
「ええと、じゃあ……」
そう言って緋勇が手に取ったのは、根付と良く似た兎がついたストラップだった。
ただ根付がうずくまる兎に対して、こちらは今にも飛び跳ねそうな勢いのある兎。
「あ、えと、その根付の兎がすごく可愛かったから……駄目ですか?だったら他のを……」
その兎を見た犬神が、何とも言えない顔になったので緋勇は慌てて他のストラップを探し始めた。
「いや、駄目も何も、それが気に入ったんならいいさ。店主、これも一緒に会計を頼む。」
「おおきに。」
そうして飛び跳ねる兎のストラップは、緋勇の携帯にぶる下がることになった。
二人は店を出ると、緋勇は慌てたように表通りに飛び出した。
「じゃ、じゃあ、俺行きますね。友達待たせてるんで。その、コレ、ありがとうございました。」
少し照れながら犬神に礼を述べると、そのまま駆けだして行ってしまった。
その駆けて行く緋勇の後姿を見ると、まるであの兎のようだと犬神は思いながら、自分の右手を見た。
あの時、俺は何をしようとした?
自分の行動の意味が分からずに、犬神は戸惑っていた。
そして緋勇も、兎のように跳ね回る自分の胸の意味が分からずに戸惑っていたのだ。