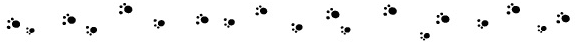▼2
帝の居室に着いた緋勇は、特に帝の側近く、御簾越しに顔が見れるところまで召された。帝がこれほどに怪異を恐れているには訳がある。
一月ほど前に遡る。
帝の夢に一人の女が現れ、こう告げたのである。
「羽根の如き軽い甘言で我を謀り玩び、飽きたとなれば芥の如く我を捨てた憎き御方。ああそれでもなお貴方を愛しいと思ってしまう業の深き我の想い。この渇きを癒す為貴方の喉を私に下され。その柔らかな喉を我の爪で掻き切らせてたもれ……。」
その女人は、帝が戯れに通った市井の女であった。
何時の時代でも、男が女を捨てる、女が男を捨てる、よくある事だが、とにかく帝はその女人の呪詛ともとれる言葉にすっかり怯えてしまい現在に至る、という訳だ。
「今日も、今日も朕の夢に現れおった……あの女は妖だッ!!朕は、朕は呪い殺されるッ!助けてたも、助けてたも、ああ緋勇朝臣、助けて……」
緋勇が思案にくれていると、帝の怯えた声が耳に入ってきた。
「主上、そうならぬ為に夜毎皆で主上をお守りいたしておりまする。」
「さ、されと今日あの女はこう言ったのだ!!高く笑いながら無駄じゃと、何もかも無駄じゃとッ!!!」
その取り乱しようは、日の本の朝を治める方とは到底思えぬほどであった。
どうして彼が、帝が政に興味を示さず日々を奔放に過ごすようになったか、まさかその原因が自分にあるとは露程にも思っていない緋勇には分からなかった。
そう、帝が緋勇の朝臣を自分の側近くに仕えさせたのも何も彼が気に入りだった訳ではないのだ。
幼い頃から何かと異母弟と比べられ、今上帝となった今でも彼が謀反を起こすのではないかと戦々恐々としており、自分の目の届く範囲に彼がいないと不安で堪らなかったのだ。
今回の召しも、自分に振りかかる厄災の盾とし、あわよくば死んでくれればいいと謀っている帝の胸中など知らず、緋勇は必死に帝を宥めるのだ。
「主上、今も陰陽寮の方々が主上をお守りするため夜通しで呪詛返しの法を行っております故、どうかお気を確かに……。」
緋勇が更に言葉を続けようとした時だった。
突如居室に風が吹き荒れた。
咄嗟に緋勇は帝の前に立ちはだかりその邪風を遮ったが、突如のことに側に控えていた公達は取り乱し我が我がと先を争ってその場から逃げ出そうとする有様。
その姿に軽く舌打ちすると、緋勇は腰の長物を引き抜き公達を叱咤する。
「お気を確かに保たれよ!貴公たち帝をお守りせずして逃げようというのか!誰か!誰かあるか!!衛士たち周囲を固めよ!陰陽師た疾く参られよ!!!」
「無駄じゃ。」
その声は唐突に聞こえた。
背後で帝の小さな悲鳴が聞こえ緋勇は反射的に身構え太刀を正面に向けた。
緋勇の視界の中、公達が慌てふためく中に、異様な静けさを纏った女が立っていた。
風はとっくの内に凪いでいるのに、女の髪はまるでそれが意思ある生き物の如くざわわと蠢いてる。
「許せ、ゆ、許せ赤音ッ!!ち、朕が悪かったッ!!!」
背後から帝の情けない声が響く。
「許せ?はて面妖なことを言う男じゃ。これほどまでにそなたを愛しいと想うておる我が何を許せと言われる筋があるというのじゃ?ただそなたは我と一緒に行くだけじゃ。さあ……」
そう言うと、赤音と呼ばれた女はゆるりと白蛇の腕をゆるりと帝に伸ばそうとした時、緋勇は女と帝の間に立ちはだかった。
抜き身の太刀を放り投げ、日本では見られない大陸の武型を取った。
「なんじゃ?お前は何じゃ?我と彼の方との逢瀬を邪魔するつもりかえ?」
「私は、私は貴女を哀れに思う。だが、この方はこの国の礎、御柱、無くてはならぬ方。どうか、どうかお怒りを鎮めては下さらぬか?」
「おお!ひ、緋勇朝臣!たたた、助けてたもッ!!」
縋り付こうとする帝を何とか宥めながら緋勇は女の出方を待った。しかし……
「ふふふ、ふははははッ!!勇ましきことよ。人風情が勇ましきことよ。震える身体で何とか時間を稼ごうとしておるな。」
緋勇の思惑は女にはお見通しだった。
「だが、時間を稼いだところで助けなんぞ来ぬぞえ。」
言われて初めて緋勇は周囲の音がしない事に気がついた。
そして改めて周囲を見渡せば、視界では慌てふためく公達が見えるのに、まったくこちら側に気付いてはいないようだ。
緋勇は知らず臍を噛んだ。
「ふふふ、音だけではないぞ。ほれ次は目じゃ。」
耳がまったく聞こえてないというのに、女のその挑発的な言葉だけが頭に響き渡る。そして緋勇の視界は真っ暗な闇に閉ざされた。
「!!」
「ほれ次は触覚じゃ。」
女の言葉通りに、来ている着物の感覚さえ失った。
「そこで柱のように立っておれ。我と彼の方との逢瀬、邪魔するでないぞ。」
目も耳も、感覚さえ失っている緋勇だったが、直感で女の前に立ちはだかる事に成功した。
「うぬれ……、もう容赦はせぬぞ。」
そう言って、女は恐ろしく伸びた爪を緋勇に振り下ろそうとした時、空気を切る音と共に二人の間に青い炎が燃え盛った。
いや、よく見れば鏃の部分が青く燃えている矢が二人の間に射られたのだ。
また一つ、また一つ、ひゅん、という音と共に青い炎が二人の間に突き刺さる。
青い炎が一つ一つ増えるたびに、緋勇の視界、聴覚、触覚が元に戻っていく。
そして青い炎はまるで生き物のように一斉に女に襲い掛かった。
「おお!この炎は!?熱や熱や、止めてたも、止めてたも!!」
すると女は青い炎に中てられたのか自身が赤い炎に包まれそのまま消えてしまったのだ。
ようやく、怪異が治まったようだ。
辺りには静けさが戻り、公達は呆然と床に座り込んでいた。
帝はあまりのことに気を失い倒れてはいたが、呼吸もしっかりしており命には別状はないようだ。
そのことでようやく緋勇も気が抜けたのか、その場にぺたんと座り込んでしまった。
そして何気なく庭に目をやると、そこには先ほどの武士団で見かけたあの放免の男が、弓を手にし緋勇を見つめていたのだった。