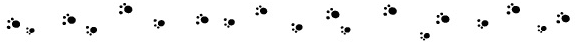▼6
犬神が緋勇の屋敷に迎えられて数日がたとうとしていた。実際、犬神が緋勇に付き従う随身として動くには暫く時間がかかる為、その間犬神は緋勇家の客分として扱われていた。
まず上司である蔵人頭に相談して今回の怪異が解決するまでとの約束で、内密に主上に奏上して許可を得て改めて表立って犬神を登用する、という算段になった。
その間、犬神は緋勇の屋敷に滞在することになったのだが、型苦しいことが嫌いな性分である犬神は、主人の命であればと、嫌な顔一つせずに犬神を世話しようとする優秀な女房達に癖々し、勝手に屋敷内をうろうろしていた。
神出鬼没である彼はいつの間にか、緋勇の部屋に入り込む事もしばしば。その度に京一は飛んできて犬神を追い出そうとする。犬神のほうはどうやら相手にしておらぬ様子だったが。
緋勇はというと、改めて犬神という男の素性が不思議に思っていた。
話をしていても、放免とは思えぬほど闊達で、その知識の深さは相当なものだと話の節々から伺える。
蔵人という仕事は多忙を極める役職であるから、普段緋勇達蔵人は内裏に仮住まいをしそうちょくちょく屋敷にはいないのだが、偶然にも犬神が滞在している間は物忌みの期間であったため、犬神と話をする機会を得ていたのだ。
その夜も、犬神は台所から失敬したであろう酒を片手に緋勇の部屋を訪れた。
「お前は飲まないのか?」
ついと杯を進められ受け取るが、緋勇は舐めるようにしか酒を飲まなかった。
「私は、あまり強くないので……」
進められれば一応は飲むが、それ以上は飲まないようにしているのだ。
「そうか……」
緋勇がそう言うと、犬神はそれ以上進めようとはせず、勝手に手酌でどんどん酒を開けていった。
今宵は満月。
紺青の夜空に白く輝く月が二人を照らし出している。
暫く会話も無いまま、何時の間にか酒は飲み干されていた。
「お酒を、もっと持って越させましょうか?」
「いや、いい。」
犬神の短い応えに、緋勇はどうやって会話を続けようかと思案していたが、犬神のほうから声をかけてきた。
「どうした?俺に何か聞きたいことがあるんだろう?」
「あの、件の怪異のことですが……」
「ああ、その事か。それが何か?」
「その、あの怪異を起こした女人とはどういう、縁がおありで?」
そう、犬神はかの女人と少なからず縁があると言った。
そしてその女人を救うために自分は来たのだと、検非違使庁で緋勇に言ったのだ。
緋勇はずっと、その事が気になっていたのだ。
「お前、通う女はいないのか?」
だが犬神は質問には答えず逆に緋勇に問うてきた。
「いきなり、何を……。」
緋勇はほんのりと頬を染め上げ、ちびりと杯の酒を舐めた。
「で、どうなのだ?」
どうやら犬神は緋勇の質問には答える気はさらさら無いようだ。
仕方なく緋勇はそっと月を仰ぎ見て、過去の女人たちを思った。
「私は、どうやら女人を不幸にする。」
興味をそそられた犬神が緋勇を見た。
「ほう?」
その視線から逃れるように緋勇は青白い月を見続けた。
「これでも密かに思いを通わせた女人は幾人かはおりました。ですが……」
一旦言葉を切りながら、どう答えてよいものかと緋勇は言葉を選び選びながらぽつりと話し始めた。
「どういう訳か、私が思いを寄せた女人は全て不幸な末路を……」
一人は、家が傾き零落しそのまま行方知れずになった。
一人は、夜毎恐ろしき声が聞こえると言いながら、最後は狂ってしまった。
一人は、そんな緋勇の噂をどこからか聞きつけ、そのまま去っていってしまった。
「私には、何か憑いているのでしょうか?それとも私自身がそういう因果を背負っているのでしょうか?彼女達だけじゃない、母も、私を産んだ母も不幸な最後をッ…」
堪らず緋勇は犬神の襟を掴みながら、まるで責めるように答えを求めた。そんな緋勇を犬神は静謐な光を湛えた双眼で見つめる。
「どうしてそれを俺に聞く?」
自分の取った行動に恥じたのか、緋勇はそのまま顔を伏せた。
「貴方は、陰陽師達がてこずった怪異を退けた程の力の持ち主です。ですから何か分かるのではないかと……」
「お前には、何も憑いておらんよ。お前の因果など、俺には見えるはずも無い。」
突き放すような物言いに、緋勇は犬神が怒っていると思い襟を掴んだままの手を離そうとした。が、犬神の手が緋勇の手を捉え叶わなかった。
「あの、す、すいません。少し酔うているようです。見苦しいところをお見せしました。」
何とか離れようと、もがく緋勇の頬をするりと犬神の指がなぜた。
驚いた緋勇が顔を上げると、そこには見たことも無い犬神の目が間近に迫っていた。
この薄闇の中、己が光を発する両眼。
緋勇の背筋にぞくりと何かが走る。
「あの……」
「あまり女の肌を知らぬようだな。」
犬神は緋勇の匂いを辿るように額から鼻梁、そして唇を掠め首筋を犬神の鼻先が辿っていく。
犬神の鼻先が、そして唇が触れるか触れないかの距離を保ちながら、羽のように掠めていく心地にむず痒さを感じながらも緋勇は動けないでいる。
これ以上は止めて欲しいと懇願するように緋勇は改めて犬神の瞳を見た。
月に照らし出されているのか、青い光を湛えた眼光の美しさと鋭さに、喉までせりあがった懇願の言葉が垂下されてしまう。
「い、犬神殿?」
「男は知らんのか?お前達貴族の間では珍しくもなかろう。」
まるで楽しみながら、歌うように犬神は鼻先で、指で、言葉と舌で、緋勇の身体を吟味していく。
「あの……ッ!」
「よくこの器量で知らぬまま来れたものだ。ああ、それともあの男の庇護のおかげか?まあそんな事はどうでもいい。」
ここまで来れば、いかな鈍いといわれる緋勇にも分かる。
犬神は自分を欲している。
そのあからさまな欲が、緋勇の下肢に当たりその硬さと質量に緋勇は戦慄いた。
自分よりも大きく、強い者が自分を組み敷こうとする恐怖が緋勇を快楽から遠ざけており、その証拠に緋勇自身は犬神の手の中で縮こまってしまっている。
その恐怖をあやすように、そして慰めるように犬神は大きな身体で緋勇を抱きしめ、耳元で昼間とは違う柔らかな声で囁いた。
「俺はお前を捨てた女達とは違う。全て俺に任せて目を閉じていろ。」
言葉に従い、緋勇は目を閉じた。
そう、緋勇はとっくの昔に犬神の手中に落ちていたのだ。